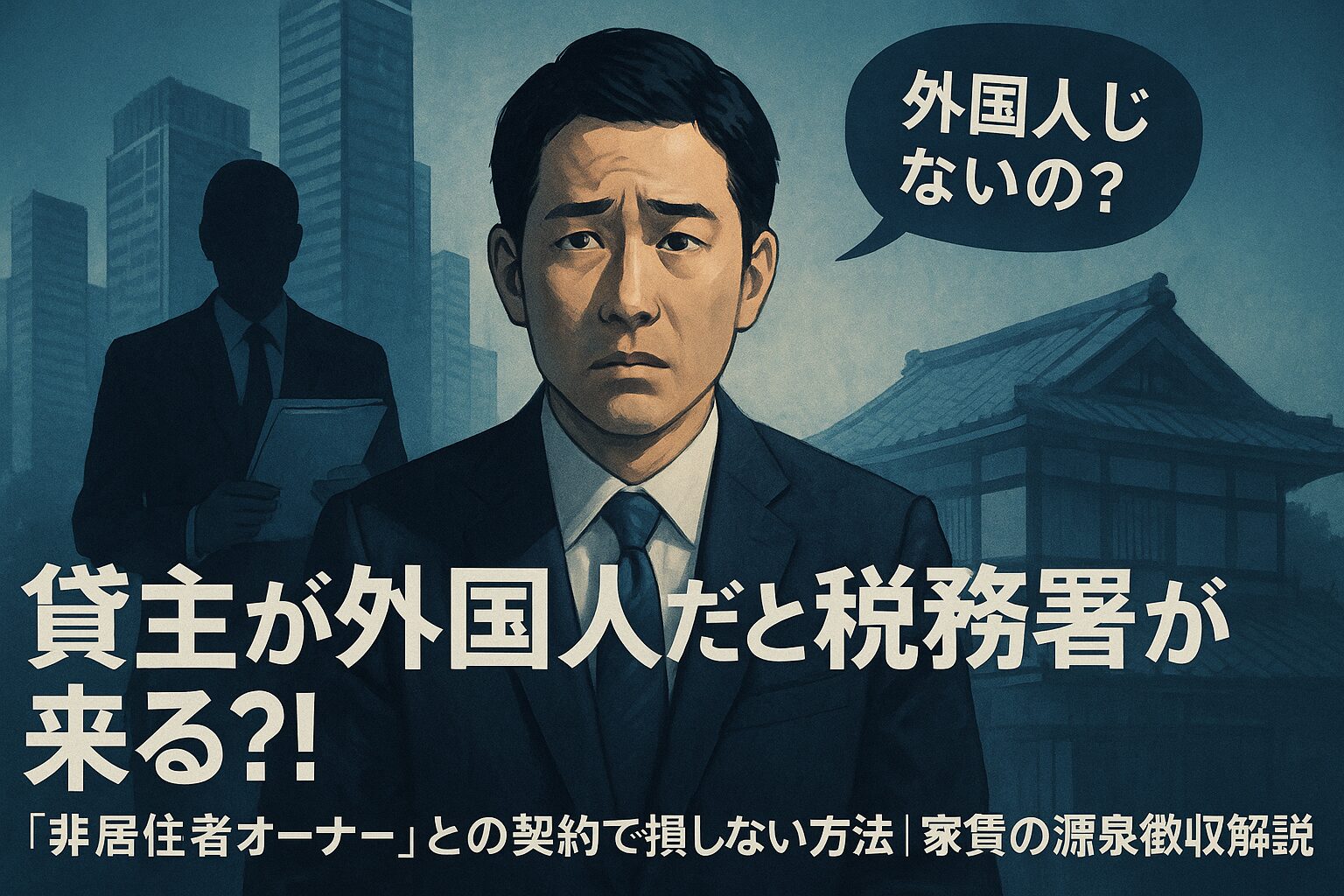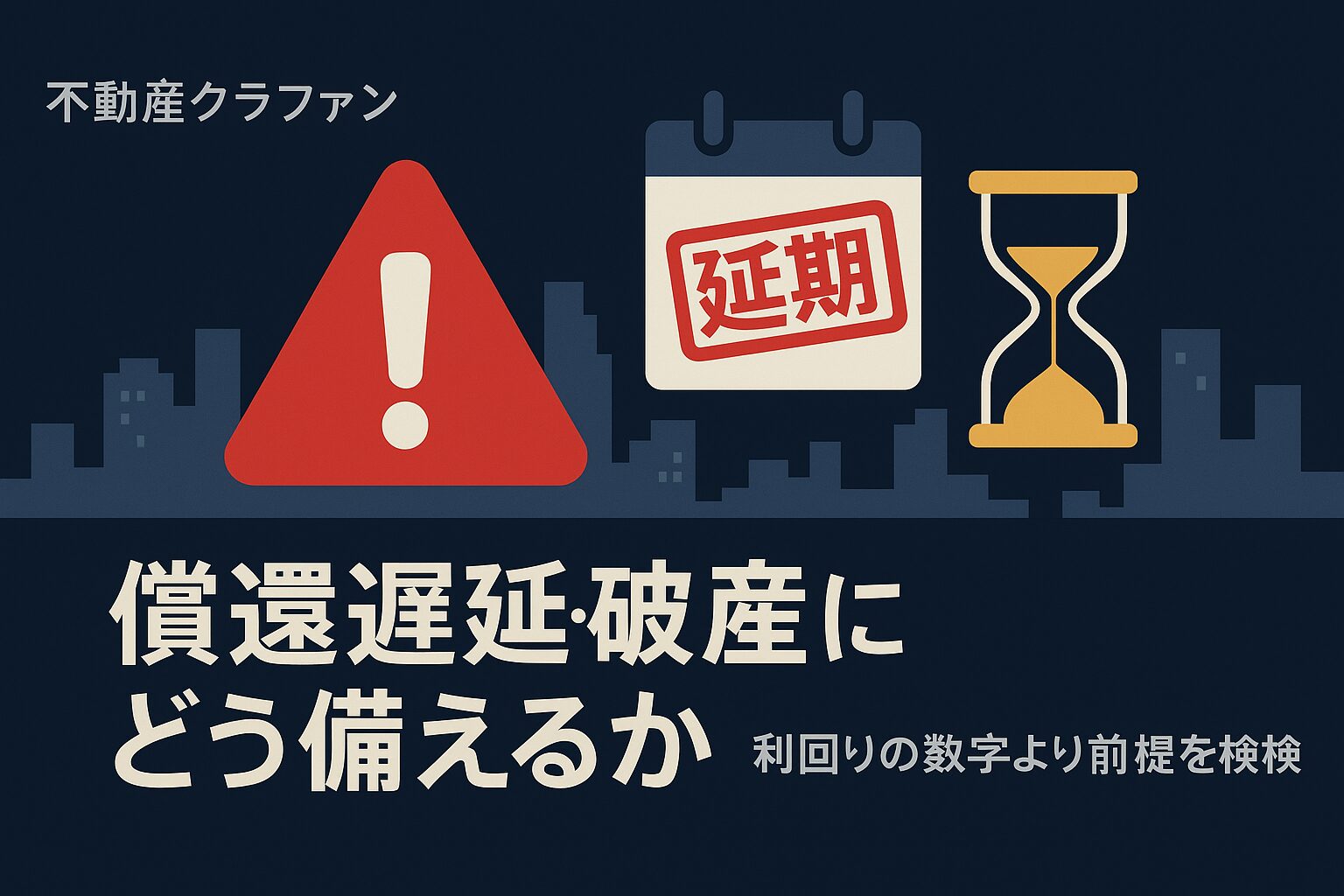- はじめに:もう「家計の迷子」にならないために
- 第2章 事前準備:現状をサクッと見える化
- 第3章 目標設定:貯蓄率と優先順位を決める
- 第4章 設計アプローチ:自分に合う方式を選ぶ
- 第5章 カテゴリ設計と配分比率の目安
- 第6章 月次キャッシュフローに落とし込む
- 第7章 サンプル基本予算
- 第8章 変動収入・ボーナス・臨時支出の扱い
- 第9章 運用と見直しのルーティン
- 第10章 固定費&変動費の定番コストダウン
- 第11章 よくある失敗と対処
- 第12章 そのまま使えるテンプレ&チェックリスト
- 12-1 月次予算テンプレ(30万円例)
- 12-2 支払日カレンダー(雛形)
- 12-3 口座設計シート(4口座モデル)
- 12-4 特別費(シンキングファンド)台帳
- 12-5 封筒マスター&週チャージ
- 12-6 ダッシュボード(Sheets/Excel式)
- 12-7 スプレッドシート列テンプレ(家計明細)
- 12-8 週次・月次チェックリスト(印刷OK)
- 12-9 YAML家計プリセット(メモ用・上級者)
- 12-10 用語ミニ辞典(要点だけ)
- 最後に:人生の「選択肢」を増やすために
はじめに:もう「家計の迷子」にならないために
もしあなたが、毎月生活費がギリギリで将来が不安なら、この話はきっとあなたの人生を変えるきっかけになります。
かつて、私自身もそうでした。料理人として働き、食には人一倍こだわりがあったものの、お金の管理は大の苦手。家計簿を始めては三日坊主、気づけばクレジットカードの請求額に怯える日々でした。
「どうしてこんなに頑張っているのに、お金が貯まらないんだろう…」
そんな迷路にハマっていた私を救ってくれたのが、今回お話しする「基本予算」という考え方です。
家計管理と聞くと、「家計簿をつけなきゃ」と思うかもしれません。でも、家計簿は単なる「過去の記録」。いくら丁寧に記録しても、未来のお金の使い方をコントロールする力はありませんでした。
私が辿り着いた答えは、まったく逆の発想です。
「家計簿=過去を記録」ではなく、「基本予算=未来の配分を先に決める」
この考え方に切り替えた瞬間、私のお金に対する見方は180度変わりました。
この記事では、私が実際に生活防衛資金を貯め、投資を始められるまでになった具体的な方法をすべて公開します。特別なスキルは必要ありません。ただ、この「基本予算」という仕組みを、あなたの生活にインストールするだけです。
さあ、私たちと一緒に、お金のストレスから解放される第一歩を踏み出しましょう。
「私も以前、生活が苦しくてどうしようもなかった時期がありました。節約しようと必死でした。でも、どれだけ頑張ってもなかなか成果が出なくて、本当に心が折れそうになったんです…」そんなときに相談👉基本予算のクイック定義
- 目的: 毎月の収入を「固定費・変動費・貯蓄/投資・特別費」に標準配分して、迷いとムダな意思決定を減らす。
- 単位: 月(+年1回や季節の支出は「積立」で月割り)。
- 姿勢: 「余ったら貯める」ではなく、「先に貯める(先取り)」。
予算と実績の関係
- 予算: 月初(または給料日)に決めた「配分表」。
- 実績: 月末に確定した「結果」。
守るべきは予算(ルール)です。実績はあくまで、ルールのズレを見つけ、学びを得るための材料に過ぎません。実績が予算とずれたら、翌月の配分や運用を微調整すればいいだけ。完璧を目指す必要はありません。
標準世帯が基本予算を持つメリット
- 固定費が多くても安心感が増す住宅、保険、通信、教育など、外せない支出が多くても、上限を先に決めることで赤字頻度が下がります。
- 季節イベントで家計が崩れない学校行事や帰省、レジャー、車検などを特別費として毎月積み立てておけば、出費の多い月でも家計は平常運転です。
- 家族の意思決定が速くなる「この費目はいくらまで」が共有されるため、買い物や外食での相談コストが激減します。
- 貯蓄率が安定収入が増減しても「先取りルール」で最低ラインを確保できます。
基本の4ブロック(標準世帯版)
家計をシンプルに4つの箱に分けるだけで、お金の流れが驚くほど明確になります。
1. 固定費: 住居、光熱、通信、保険、教育、サブスクなど、毎月ほぼ一定の支出。
2. 変動費: 食費、日用品、外食、レジャー、被服など、使い方次第で増減する支出。
3. 貯蓄・投資: 生活防衛資金の積立、教育費、老後資金、つみたて投資など。
4. 特別費(年1回・季節費): 帰省、旅行、車検、入学・進級など、大きな支出を月割りで積み立てる「シンキングファンド」。
用語ミニ解説
- 先取り貯蓄(Pay Yourself First): 給料が入ったら「最初に」貯蓄・投資へ自動振替する方法。
- シンキングファンド: 将来の大きめの支出を、毎月コツコツ取り置きして当月の家計を守る仕組み。
よくある誤解と解消
- 「予算は細かすぎて続かない」→ はじめは4つの大きな箱だけでOK。慣れてきたら、食費など主要な項目だけ細分化しましょう。
- 「ボーナスで調整すればいい」→ ボーナスは「追加の目標達成」に充てる前提です。日常の家計は月単位で完結させることが鉄則です。
- 「クレジットカードは後払いだから予算が見えない」→ 翌月の支払いを今月の実績に反映させるルールを固定します。アプリ連携か手動メモで十分管理できます。
第2章 事前準備:現状をサクッと見える化
お金を管理する前に、まずは現状を把握しましょう。難しく考える必要はありません。この章のゴールはたった3つです。
- 手取り月収(世帯合計)を確定
- 固定費・変動費・特別費の「いまの姿」を把握
- 予算に流し込める最小限のデータ表をつくる
「完璧」を目指さず、「8割見えればOK」という気持ちで進めてください。
1. 15分クイック診断
まずは直近1か月の入出金履歴を、銀行やクレジットカードのアプリで確認しましょう。
- 大きい支出トップ5を書き出す(家賃、保育料、保険、通信、食費など)
- 固定費の合計とおおよその貯蓄額をメモ
この段階で、「固定費が手取りの何割か」をざっくり把握できれば十分です。
2. 3か月ミニ棚卸し:最小コストで正確に
ここからが本番。直近3か月の銀行口座、クレジットカード、交通系・QR決済の明細を棚卸しします。やることは「取込→整形→タグ付け」の3ステップだけ。
2-1 取込(CSV推奨)
主要口座とカードの明細をCSVでダウンロードするのがおすすめです。現金支出はレシートがなくても、ATM引き出し額を「現金費目」として一括計上すれば問題ありません。
2-2 整形(列をそろえる)
表計算ソフトで、以下の列を作成しましょう。
| 列名 | 説明 | 例 |
| 日付 | 購入日 or 引落日 | 2025-07-12 |
| 内容 | 店名・サービス名 | 楽天モバイル |
| 金額 | 支出はマイナス、収入はプラス | -2,980 |
| 種別 | 支出/収入/振替 | 支出 |
| 支払手段 | 現金/デビット/クレカ/QR | クレカ |
| 区分 | 固定/変動/特別/貯蓄 | 固定 |
| カテゴリ | 後述の「基本マップ」から選択 | 通信 |
| メモ | 任意 | 3GBプラン |
ワンポイント: クレジットカードは「購入日」で支出として計上し、翌月の「引落し」は振替にすることで、二重計上を防げます。
2-3 タグ付け(半自動でOK)
ルールを決めて、取引にカテゴリのタグを付けていきます。
- 楽天モバイル → 通信
- 保育園 → 教育
- Amazon・楽天 → 日用品 or 特別費
迷う取引は一旦「その他」に入れておき、月末にまとめて振り分ければ大丈夫です。
3. 家計項目の「基本マップ」(標準世帯ベース)
まずは4つの大きな箱に分け、必要に応じてサブ項目を追加していきましょう。
- 固定費(毎月ほぼ一定)
- 住居:家賃/住宅ローン、管理費、駐車場
- 光熱:電気・ガス・水道
- 通信:携帯、ネット回線
- 保険:生命・医療・火災・自動車
- 教育:保育料、学童、授業料
- その他:交通定期、サブスク
- 変動費(使い方次第で増減)
- 食費(内食)/外食・カフェ
- 日用品・ドラッグ
- 交通(都度)/タクシー
- 娯楽・レジャー
- 被服・美容
- 医療・ヘルスケア
- 交際・ギフト
- 貯蓄・投資
- 生活防衛資金積立
- 教育資金/老後資金
- つみたて投資(iDeCo/NISA等)
- 借入追加返済
- 特別費(年1回・季節)
- 帰省・旅行
- 車検・自動車税・保険更新
- 家電・家具更新
- 入学・進級・学用品
- 固定資産税・住民税(給与天引き外)
ポイント: 特別費は「シンキングファンド」(目的別の取り置き口座やデジタル封筒)で毎月積み立てるのがコツです。
4. 「固定か変動か」の判定クイックルール
- 契約・請求書ベースで毎月/毎年発生 → 固定費(例:保険、通信)
- 買い物ベースで頻度や金額が変わる → 変動費(例:食費、外食)
- 年1〜2回の大きな支出 → 特別費に登録し月割りへ
5. 年間・季節費を月割りにする
例えば、年間12万円の車検費用(2年に1回)は、月々5,000円。年1回の8万円の帰省費用は、月々約6,700円。
このように、年間合計を12で割って、毎月「特別費口座」へ自動で積み立てるのが鉄則です。
6. 指標をひとまず出す(3か月平均でOK)
棚卸ししたデータから、以下の3つを計算しましょう。
- 手取り月収(世帯)
- 固定費比率 = 固定費合計 ÷ 手取り月収
- 貯蓄率 = (貯蓄・投資・繰上げ返済)÷ 手取り月収
目安: 固定費比率は**〜50%、貯蓄率は15〜20%**確保できると理想です。
7. 支払日カレンダー&口座マップの下準備
給料日やクレジットカードの引き落とし日をカレンダーに書き込み、どの口座から何が引き落とされるかを線で結んでみましょう。
8. よくある詰まりポイントと対処
- 家族カードの混在 → 名義ごとに支払手段の列を分けましょう。
- Amazonなどの複合購入 → メモに「内訳:食材2,000/家電3,000」と残すだけでもOKです。
- 現金の用途不明 → ATM引き出し額を「現金費」としてまとめ、3か月平均で額を固定します。
9. この章の成果物(チェックリスト)
- 3か月分の明細CSVを1シートに統合した
- 固定/変動/特別の大分類を付与した
- 年間・季節費のリスト化&月割り額を算出した
- 固定費比率・貯蓄率を計算した
第3章 目標設定:貯蓄率と優先順位を決める
この章のゴールは**「何のために、毎月いくら先取りするか」を明確にすること。**目標がなければ、家計管理は続きません。
1. 優先順位の地図(標準世帯の基本順)
家計管理には、正しい道のりがあります。まずは下の地図を頭に入れてください。
- **生活防衛資金(緊急資金)**の確保
- 高金利の借金の圧縮(リボ・カードローン等)
- 保険・保障の適正化
- 中長期の積立投資(教育・老後・将来の大口資金)
- 楽しみ・経験のための特別費(旅行・イベントなどの「計画消費」)
2. 生活防衛資金の規模を決める
これは、病気や失職など「収入がゼロになっても生活を守る」ための現金バッファです。
- ステップA: 「最低生活費」を算出する。目安は通常の月支出の70〜80%です。
- ステップB: 世帯タイプ別の月数を決める。
| 世帯タイプ | 目安月数 |
| 共働き・収入安定 | 3か月分 |
| 片働き or 自営業/変動大 | 6か月分 |
| 扶養家族多・持病・転職直後 | 6〜12か月分 |
計算例: 最低生活費22万円/月の場合、共働きなら3か月分で66万円。片働きなら6か月分で132万円が目安です。
3. SMART目標で「何のために」を言語化
目標は、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、期限付き(Time-bound)のSMART目標にしましょう。
- 短期(〜1年): 「2026年3月までに生活防衛資金90万円を達成する(現在40万円、毎月4万円+ボーナス10万円)」
- 中期(1〜5年): 「2028年3月までに教育資金150万円(月2万円+児童手当の全額取り置き)」
- 長期(5年以上): 「2045年までに老後資金1,500万円を積み上げる(つみたて投資:月3万円、年3%想定)」
4. 先取り額の公式(標準世帯版)
月の先取り総額 = 貯蓄・投資の先取り + 特別費(シンキングファンド)の月積立
- 貯蓄・投資の先取り: 手取りの15〜20%を目標に設定します。
- 特別費の月積立: 年間イベントや大型支出の合計を12で割った金額。
数値例(手取り30万円):
- 貯蓄・投資:20% = 6万円
- 特別費の月積立:3万円
- 先取り総額: 6万円 + 3万円 = 9万円
この9万円を、給料日に自動で3カ所(生活防衛資金、つみたて投資、特別費積立)へ分配する仕組みを作ります。
5. 借入返済の組み込み方
高金利の借金がある場合は、優先順位を最上位に。最低返済額に加えて、追加返済分を先取り額に含めます。
6. 児童手当・ボーナスの扱いルール
- 児童手当: 全額を教育資金へ自動振替。最初から**「無かったもの」**として管理することが、教育資金を確実に貯める秘訣です。
- ボーナス: あらかじめフォーミュラを固定します。
- 例)防衛資金20%/投資30%/特別費30%/自由10%/寄付10%
このルールを決めることで、「ボーナス=使い切り」を防ぎ、家計の貯まるスピードを劇的に加速させます。
7. 目標マップ(そのまま使えるテンプレ)
| 目的 | 期限 | 目標額 | 現在額 | 月先取り | ボーナス配分 | メモ |
| 生活防衛資金 | 2026/03 | 900,000 | 400,000 | 30,000 | 100,000 | まず3か月→6か月 |
| 教育資金 | 2028/03 | 1,500,000 | 200,000 | 20,000 | 50,000 | 児童手当全額転用 |
| 老後資金(投資) | 2045/12 | 15,000,000 | 300,000 | 30,000 | 0 | 積立NISA/iDeCo |
| 旅行(特別費) | 2026/08 | 200,000 | 20,000 | 8,000 | 20,000 | 夏・冬で山をつくる |
第4章 設計アプローチ:自分に合う方式を選ぶ
家計管理には様々な方法がありますが、ここでは4つの代表的な方式を比較し、あなたの家計に合う運用レシピを決めます。
結論から言うと、標準世帯は**「先取り貯蓄(Pay Yourself First)+デジタル封筒」を土台に、50/30/20は上限チェック、必要ならゼロベース予算で一度だけ細かく設計**するハイブリッド型が一番続きます。
1. 方式の全体比較
| 方式 | 何を決める? | 継続のしやすさ | 精度 | カード払いとの相性 | 向いている世帯 |
| 50/30/20ルール | 手取りを「必要50/欲求30/貯蓄20」に配分 | ◎ | ◯ | ◎ | 初めての人、ざっくり把握したい |
| ゼロベース予算 | 1円まで全項目に割り当て、残高0に | △ | ◎ | ◯ | 一度フル設計したい、支出がブレやすい |
| 先取り貯蓄(PYF) | 給料日に先に貯める額を自動振替 | ◎ | ◯ | ◎ | 忙しい共働き、時短重視 |
| 封筒・サブ財布 | 変動費を箱ごとに管理 | ◎ | ◯ | ◎ | 食費・外食がブレがち、現場で使い過ぎる |
2. クイック診断:あなたはどの型?
- A. 毎月「先取り額」が決まっていない → 先取り貯蓄を核に
- B. 変動費が膨らむ → 封筒(デジタル)を追加
- C. 固定費が高い気がする → 50/30/20で上限チェック
- D. 一度ちゃんと設計してスッキリしたい → 月1回だけゼロベースで土台を作る
3. 実装レシピ(手取り30万円・標準世帯の例)
3-1. 50/30/20ルール(「上限の物差し」として)
- 標準配分: 必要50%=15万円/欲求30%=9万円/貯蓄20%=6万円
- カスタム: 特別費(シンキングファンド)を貯蓄に含めて**「貯蓄+特別=30%」**とすることも可能です。
固定費合計が50%を超えていないか確認し、超えていれば通信・保険などの契約見直しや、住宅費の借換えを検討しましょう。
3-2. ゼロベース予算(最初の一回「骨組み作り」)
手取り30万円を1円残らず割り当ててみましょう。これはあくまで「設計ドキュメント」なので、日々の運用はもっとシンプルで大丈夫です。
- 先取り(計9万円): 防衛資金3万、つみたて投資2万、追加返済1万、特別費積立3万
- 固定費(計14.5万円): 住居8.5万、光熱1.5万、通信0.6万、保険1.2万、教育2万、サブスク0.7万
- 変動費(計6.5万円): 食費3.8万、外食0.8万、日用品0.8万、交通0.5万、医療0.3万、レジャー0.3万
3-3. 先取り貯蓄(Pay Yourself First)の実装
給料日の翌営業日に、自動振替を設定します。
- 貯蓄・投資用口座へ6万円
- 特別費用口座(デジタル封筒)へ3万円
この設定が済んだら、あとは残りを「使っていいお金」として変動費封筒に配分するだけ。これで、貯蓄が最初から達成されます。
3-4. 封筒・サブ財布(デジタル封筒)の運用
変動費を**「月→週の定額チャージ」**にすることで、使い過ぎを防げます。
- 変動費合計6.5万円 ÷ 4週 ≒ 16,250円/週
- 週の残りは翌週へ繰り越し、月末に残ったら特別費へ移すルールに。
第5章 カテゴリ設計と配分比率の目安
ここでは、各カテゴリに**「上限」**を設定し、毎月の迷いをなくします。
1. 全体バランスの目安
| ブロック | 目安比率 | 30万円の上限例 | ねらい |
| 固定費 | 45–50% | 13.5万–15万 | 高止まりしやすいので上限管理 |
| 変動費 | 20–30% | 6万–9万 | 封筒(週チャージ)で現場抑制 |
| 貯蓄・投資 | 15–20% | 4.5万–6万 | 先取りで自動達成 |
| 特別費 | 5–10% | 1.5万–3万 | 季節イベントの平準化 |
2. 固定費のカテゴリ別「上限レンジ」
| カテゴリ | 指標(手取り比) | 30万円の上限例 | 見直しの勘所 |
| 住居 | 25–30% | 7.5万–9万 | 更新期の家賃交渉、借換え |
| 光熱 | 5–8% | 1.5万–2.4万 | 料金プラン・電力会社見直し |
| 通信 | 2–4% | 0.6万–1.2万 | 格安プラン、家族割 |
| 保険 | 3–6% | 0.9万–1.8万 | 保障のダブり削減 |
| 教育 | 3–8% | 0.9万–2.4万 | 児童手当の全額取り置きと併用 |
3. 変動費の目安(封筒運用に最適化)
| カテゴリ | 指標(手取り比) | 30万円の上限例 | 運用ルール |
| 食費(内食) | 10–15% | 3万–4.5万 | 週2回まとめ買い |
| 外食・カフェ | 2–6% | 0.6万–1.8万 | 別封筒にして回数管理 |
| 日用品・ドラッグ | 2–4% | 0.6万–1.2万 | 定番品は定期便 |
変動費は「週チャージ」が非常に有効です。
4. 特別費(シンキングファンド)の設計
前年の実績を洗い出し、年額合計を12で割って、毎月「特別費口座」へ自動積立。発生月にその口座から支払います。
5. ベース配分の完成形(30万円のサンプル)
| ブロック/カテゴリ | 月額 | 手取り比 |
| 貯蓄・投資(先取り)合計 | 60,000 | 20.0% |
| 特別費(積立) | 30,000 | 10.0% |
| 固定費 合計 | 145,000 | 48.3% |
| 変動費(封筒) 合計 | 65,000 | 21.7% |
| 合計 | 300,000 | 100% |
この配分は、第4章のハイブリッド運用にそのまま当てはまります。
電気代の高騰時にも変動なしでホット安心【四つ葉電力】第6章 月次キャッシュフローに落とし込む
これまで決めた配分を「給料日→自動で流れる仕組み」に落とし込み、赤字の原因である「タイミングずれ」を根絶します。
1. 口座の役割分担(4口座モデル)
| 口座 | 役割 | 主な入出金 | 備考 |
| 入金口座 | ハブ | 給与・児童手当など | 滞留させない |
| 固定費口座 | 引落し用 | 家賃・光熱・通信・保険・カード引落しなど | 月額固定の支出専用 |
| 変動費口座 | デビット/プリペイド | 食費・日用品・外食など | 使いすぎを物理的にブロック |
| 貯蓄・特別費口座 | 目的別 | 生活防衛資金・教育・投資・特別費など | 目的別に分ける |
1つの銀行のサブ口座やデジタル封筒で代用してOKです。
2. 給料日ベースの「給料日予算」を作る
給料日の翌営業日に、自動振替を設定します。
- T+0日(給料日当日):
- 先取り①:貯蓄・投資へ自動振替(例:6万円)
- 先取り②:特別費へ自動振替(例:3万円)
- T+1日:
- 固定費口座へ必要額を自動振替(例:14.5万円)
- 毎週月曜:
- 変動費口座へ週額16,250円をチャージ
これで、貯蓄が最優先で自動的に実行されます。
3. 支払日カレンダー(ひな形)
給料日やカードの締め日・引き落とし日をカレンダーに書き込み、お金の流れを可視化しましょう。
4. クレジットカードの整列術
「購入日計上・引落し振替」を家計ルール化します。
クレジットカードは固定費専用カードと、変動費用決済に分離するのがおすすめです。
5. 週次レビュー(10分でOK)
毎週月曜の朝か夜に、以下の項目をチェック。
- 変動費封筒の残高を確認
- 冷蔵庫在庫表を更新→買い物リスト作成
- 今週の外食回数・レジャー上限を決める
- 赤字封筒があれば、同じ変動費内から借り替える(固定費・先取りは死守!)
6. 夫婦家計:運用パターン3つ
- 共同財布方式: 世帯収入を同一口座に合流し、一元管理。
- 按分方式: 固定費を収入比で按分し、変動費は各自で運用。
- ハイブリッド方式: 共同費(住居・教育など)と個人費(被服・小遣いなど)を分ける。
7. トラブルシューティング
- 月中に固定費口座が足りない → 下限バッファ不足。次月から「固定費×1.2倍」を常時キープ。
- 封筒が毎週赤字 → 週チャージ額を増やすか、買い物回数を週2回に制限。
- ボーナス頼みで平月がきつい → 特別費の年額見積もりが不足。リストを見直して月積立を増額。
第7章 サンプル基本予算
ここでは、手取り30万円を前提に、独身、共働き、子どもありの3パターンを配分表で示します。
7-1. 独身(個人手取り30万円)
| ブロック/カテゴリ | 月額 | 手取り比 |
| 貯蓄・投資(先取り)合計 | 75,000 | 25% |
| 特別費(積立) | 15,000 | 5% |
| 固定費 合計 | 120,000 | 40% |
| 変動費(封筒) 合計 | 90,000 | 30% |
| 合計 | 300,000 | 100% |
7-2. 共働き二人暮らし(子なし、世帯手取り30万円)
| ブロック/カテゴリ | 月額 | 手取り比 |
| 貯蓄・投資(先取り)合計 | 60,000 | 20% |
| 特別費(積立) | 30,000 | 10% |
| 固定費 合計 | 135,000 | 45% |
| 変動費(封筒) 合計 | 75,000 | 25% |
| 合計 | 300,000 | 100% |
7-3. 子どもあり(夫婦+子1〜2、世帯手取り30万円)
| ブロック/カテゴリ | 月額 | 手取り比 |
| 貯蓄・投資(先取り)合計 | 45,000 | 15% |
| 特別費(積立) | 30,000 | 10% |
| 固定費 合計 | 150,000 | 50% |
| 変動費(封筒) 合計 | 75,000 | 25% |
| 合計 | 300,000 | 100% |
第8章 変動収入・ボーナス・臨時支出の扱い
収入や支出の「ブレ」があっても、毎月の基本予算を崩さず運用するルールを作りましょう。
1. 変動収入(月ごとにばらつく)の扱い方
- ルールの骨子:
- 過去の不調月を参考に「ベース収入」を決め、その額で基本予算を組む。
- 実収入がベースを超えた分を「余剰収入」とし、割合で分配する。
- 余剰の分配例: 防衛資金20%/投資30%/特別費30%/自由20%
- 収入変動バッファ: ベース収入の1か月分を確保。収入がベース未満の月にここから補填します。
2. ボーナス(賞与)のルール化
ボーナスは入金前に「何に使うか」を決め、自動振替の予約をしておきましょう。
- 標準フォーミュラ:
- 高金利負債(ある場合):最優先で返済
- 残額を、防衛資金20%/投資30%/特別30%/自由10%/寄付10%で分配
3. 臨時支出(突発・大型)の扱い方
支払い順序のガイドラインを決めます。
- 特別費口座の該当封筒を使用
- 収入変動バッファから一時借用
- 生活防衛資金から取り崩し
- 低金利の借入を検討
4. 特別費(年1回・季節費)の「漏れ防止」
年間イベントカレンダーを作成し、前年に発生した「未登録の大口支出」は必ず封筒化します。
インターネットでお得に自動取引!松井証券第9章 運用と見直しのルーティン
ここでは、家計を「がんばる」のではなく「回す」ための仕組みを解説します。
1. 週次ミニレビュー(10分で完了)
- タイミング: 毎週月曜の朝 or 夜
- 見るもの: 封筒(変動費)残高、今週の予定
- 手順: 封筒残高を確認、週チャージを実行、買い物リスト作成、赤字封筒があれば変動費内から借り替える。
2. 月末〆&翌月反映(30分のルーティン)
- タイミング: 給料日前後
- 手順: 実績を確定、KPIをチェック、ズレの原因を分析し、翌月の配分を更新する。
3. 予算オーバーの応急処置
- ステップ順:
- 変動費内での移し替え
- 「自由費の48時間凍結」
- 特別費の当月積立を一時停止
- 収入バッファから補填
- NG: 貯蓄の先取りを減らす、固定費口座に手を付ける
4. KPI(追うべき指標と目安)
| KPI | 定義 | 目安/アラート | 改善アクション |
| 貯蓄率 | 先取り貯蓄・投資 ÷ 手取り | ≥ 15–20% / < 10%で警告 | 先取り額を固定し、特別費を見直し |
| 固定費比率 | 固定費 ÷ 手取り | ≤ 50% / > 55%で要対策 | 通信・保険・サブスクの相見積 |
| 特別費積立達成率 | 積立実行額 ÷ 計画額 | = 100% / < 90%で要見直し | 月積立増額/イベント削減 |
第10章 固定費&変動費の定番コストダウン
生活の質を落とさず、毎月「自動で」下がり続けるコストを削ります。
1. 90分で終わる「固定費健診」の順番
- 通信(スマホ・ネット):格安回線への乗り換え、プラン見直し。
- サブスク:90日以上未使用は解約候補。
- 保険:保障の重複を削減し、免責を上げて保険料を下げる。
- 住居:更新時の家賃交渉や、住宅ローンの借換え試算。
- 光熱:料金プランや電力会社の見直し、節電の仕組み化。
2. 変動費を「仕組みで」下げる
- 食費: 「週2回まとめ買い、在庫起点、定番ローテーション」でロスを減らす。
- 外食: 別封筒にして月○回までと決め、回数を可視化する。
- 日用品: 定番リストを作り、定期便やまとめ買いを活用する。
第11章 よくある失敗と対処
家計が崩れやすい「お約束の落とし穴」を先回りで塞ぎます。
- 特別費の未計上: 年間リストを作成し、自動積立する。
- クレジットカードのタイムラグ: 「購入日計上・引落し振替」のルールを徹底する。
- 「ゼロ円項目」の落とし穴: 予備封筒を常設するか、特別費へ移管する。
- 現金のブラックボックス化: 「現金封筒」を新設し、ATM引き出し額を一括計上する。
- 夫婦家計の「モヤモヤ」: 月1回、家族会議でルールを調整する。
第12章 そのまま使えるテンプレ&チェックリスト
これまでの内容をコピペで即運用できる形に整理しました。
表テンプレ/数式/チェックリスト/用語ミニ辞典をまとめて掲載しています。目次
- 12-1 月次予算テンプレ(30万円例)
- 12-2 支払日カレンダー(雛形)
- 12-3 口座設計シート(4口座モデル)
- 12-4 特別費(シンキングファンド)台帳
- 12-5 封筒マスター&週チャージ
- 12-6 ダッシュボード(Sheets/Excel式)
- 12-7 スプレッドシート列テンプレ
- 12-8 週次・月次チェックリスト
- 12-9 YAML家計プリセット
- 12-10 用語ミニ辞典
12-1 月次予算テンプレ(30万円例)
手取り額だけ入れ替えれば使えます(数値は第5–7章の標準配分)。
| ブロック/カテゴリ | 月額 | 手取り比 |
|---|---|---|
| 手取り | 300,000 | 100% |
| 先取り(貯蓄・投資) | 60,000 | 20% |
| ├ 生活防衛資金 | 30,000 | 10.0% |
| ├ つみたて投資 | 20,000 | 6.7% |
| └ 追加返済 | 10,000 | 3.3% |
| 特別費(積立) | 30,000 | 10% |
| 固定費 合計 | 145,000 | 48.3% |
| ├ 住居 | 85,000 | 28.3% |
| ├ 光熱 | 15,000 | 5.0% |
| ├ 通信 | 6,000 | 2.0% |
| ├ 保険 | 12,000 | 4.0% |
| ├ 教育 | 20,000 | 6.7% |
| └ 定期・サブスク | 7,000 | 2.3% |
| 変動費(封筒) 合計 | 65,000 | 21.7% |
| ├ 食費(内食) | 38,000 | 12.7% |
| ├ 外食・カフェ | 8,000 | 2.7% |
| ├ 日用品 | 8,000 | 2.7% |
| ├ 交通(都度) | 5,000 | 1.7% |
| ├ レジャー・雑費 | 3,000 | 1.0% |
| └ 医療・ヘルスケア | 3,000 | 1.0% |
| 合計 | 300,000 | 100% |
12-2 支払日カレンダー(雛形)
| 日付 | すること | 出入り | 口座 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 毎月25日 | 給料日:先取り(貯蓄6万/特別3万) | -90,000 | 入金→各口座 | T+0自動振替 |
| 毎月26日 | 固定費口座へ補充 | -145,000 | 入金→固定費 | 下限=固定費×1.2 |
| 毎週月曜 | 週チャージ(変動費) | -16,250 | 変動費 | 余りは翌週繰越 |
| 5日 | 保険引落し | -12,000 | 固定費 | |
| 10日 | 先月分クレカ引落し | -45,000 | 固定費 | 購入日計上済 |
| 20日 | 通信引落し | -6,000 | 固定費 | |
| 27日 | 家賃引落し | -85,000 | 固定費 |
12-3 口座設計シート(4口座モデル)
| 口座 | 役割 | 主な入出金 | 下限/目標 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入金口座 | ハブ | 給与・児童手当→各口座振替 | 0 | 滞留させない |
| 固定費口座 | 引落し専用 | 家賃・光熱・通信・保険・クレカ引落し | 固定費×1.2 | バッファ込み |
| 変動費口座 | デビット/プリペイド | 週チャージ→日々の買い物 | 週初0〜週額 | 使いすぎ防止 |
| 貯蓄・特別費口座 | 目的別封筒 | 生活防衛・教育・投資・特別費 | 目標別 | 目的別に分ける |
12-4 特別費(シンキングファンド)台帳
| 項目 | 年額 | 月積立 | 支払月 | 支払元 |
|---|---|---|---|---|
| 帰省・旅行 | 120,000 | 10,000 | 8/12 | 特別費 |
| 車検・自動車税・保険更新 | 100,000 | 8,400 | 6/7 | 特別費 |
| 家電・家具更新 | 100,000 | 8,400 | 11/12 | 特別費 |
| 学校イベント・進級 | 80,000 | 6,700 | 3/4 | 特別費 |
| 税金(天引き外) | 60,000 | 5,000 | 6/12 | 特別費 |
12-5 封筒マスター&週チャージ
| 封筒 | 月額 | 週額目安 | ルール |
|---|---|---|---|
| 食費(内食) | 38,000 | 9,500 | 週2回まとめ買い |
| 外食・カフェ | 8,000 | 2,000 | 月○回まで宣言 |
| 日用品 | 8,000 | 2,000 | 定番リスト固定 |
| 交通(都度) | 5,000 | 1,250 | IC連携で可視化 |
| レジャー・雑費 | 3,000 | 1,500 | 余りは特別費へ |
| 医療・ヘルスケア | 3,000 | — | 月枠管理 |
12-6 ダッシュボード(Sheets/Excel式)
入力(例)
手取り = 300000
先取り合計 = 90000 # 貯蓄・投資60k + 特別30k
固定費 = 145000
特別費_計画 = 30000
変動費_実績 = 65000
赤字封筒数 = 1
封筒総数 = 6
防衛_現在 = 410000
防衛_目標 = 900000
指標
貯蓄率 = 先取り合計 / 手取り
固定費比率 = 固定費 / 手取り
封筒赤字率 = 赤字封筒数 / 封筒総数
防衛進捗 = 防衛_現在 / 防衛_目標
アラート(条件付き書式の例)
- 貯蓄率
>= 0.20→ 緑 /0.15–0.20→ 黄 /< 0.15→ 赤 - 固定費比率
<= 0.50→ 緑 /0.50–0.55→ 黄 /> 0.55→ 赤
12-7 スプレッドシート列テンプレ(家計明細)
| 列名 | 例 | 備考 |
|---|---|---|
| 日付 | 2025-07-12 | 購入日基準 |
| 内容 | 楽天モバイル | 店名・サービス |
| 金額 | -2,980 | 支出−/収入+ |
| 種別 | 支出/収入/振替 | 引落しは振替 |
| 支払手段 | 現金/デビット/クレカ/QR | 家族カード分離 |
| 区分 | 固定/変動/特別/貯蓄 | 4ブロック |
| カテゴリ | 通信/食費/外食… | 主要のみ |
| メモ | 3GBプラン | 任意 |
クレカ運用の式(例)
支出_クレカ(購入日) = SUMIFS(C:C, E:E,"クレカ", B:B,">="&月初, B:B,"<="&月末, D:D,"支出")
引落_振替 = SUMIFS(C:C, D:D,"振替", G:G,"クレカ引落")
12-8 週次・月次チェックリスト(印刷OK)
週次(10分)
- ☑ 封筒残高の確認/週チャージ実行
- ☑ 在庫表更新 → 買い物リスト作成
- ☑ 今週の外食回数を宣言
- ☑ 赤字封筒は変動費内で借り替え
月末(30分)
- ☑ 未分類ゼロ/購入日計上・引落振替を確認
- ☑ KPI:貯蓄率 ≥ 目標/固定費比率 ≤ 50%/特別費達成=100%
- ☑ ズレ原因を1つに絞り、来月の1アクション決定
- ☑ 特別費カレンダー更新/自動振替見直し
12-9 YAML家計プリセット(メモ用・上級者)
income:
take_home: 300000
payday: "毎月25日"
rules:
pay_yourself_first:
savings_invest: 60000
sinking_funds: 30000
fixed_buffer_multiplier: 1.2
weekly_topup: 16250
accounts:
hub: 入金口座
bills: 固定費口座
variable: 変動費口座
savings: 貯蓄・特別費口座
envelopes:
- name: 食費
monthly: 38000
- name: 外食
monthly: 8000
- name: 日用品
monthly: 8000
- name: 交通
monthly: 5000
- name: レジャー・雑費
monthly: 3000
- name: 医療
monthly: 3000
sinking_funds:
- name: 旅行・帰省
monthly: 10000
- name: 車関連
monthly: 8400
- name: 家電更新
monthly: 8400
- name: 学校イベント
monthly: 6700
12-10 用語ミニ辞典(要点だけ)
- 先取り貯蓄(Pay Yourself First):給料日に最初に貯蓄・投資へ振替する仕組み。
- シンキングファンド(特別費):年1回・季節の出費を月割りで積立する口座(封筒)。
- ゼロベース予算:手取り全額に役割を与え、残高0に割り当てる設計手法。
- 50/30/20ルール:必要50%/欲求30%/貯蓄20%の健全性チェックの物差し。
- アバランチ法:金利の高い負債から優先返済して総利息を最小化。
- スノーボール法:残高の小さい負債から返済しモチベ維持。
- ベース収入:過去6–12か月の下位25%の平均。最低ライン設計に使用。
- 収入バッファ:収入が少ない月の穴埋め口座。目標=ベース1か月分。
- 週チャージ:変動費を週ごとに定額補充する運用。
- 固定費比率:固定費÷手取り。≤50%が目安。
- 貯蓄率:先取り(貯蓄・投資)÷手取り。15–20%以上を目標に。
- 防衛資金(緊急資金):最低生活費の3〜6か月分の現金バッファ。
- 封筒赤字率:赤字封筒の数÷封筒総数。≤20%で運用安定。
最後に:人生の「選択肢」を増やすために
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。
家計管理は、決して「我慢」や「ケチ」ではありません。むしろ、将来の不安から解放され、本当にやりたいこと、本当に大切なことにお金を使えるようになるための「土台作り」です。
私自身、この「基本予算」という仕組みを手に入れてから、お金に対するストレスが劇的に減りました。そして、生活保護受給者でありながらも、少しずつ貯蓄や投資に回せるお金が生まれ、自分の好きな仕事や学びにも挑戦できるようになりました。
お金の知識は、人生の「選択肢」を増やすための武器です。
一歩踏み出せば、必ず道は開けます。この仕組みをあなたの生活にインストールして、お金に振り回される人生から卒業しましょう。
私もここから変われました。あなたも、必ず変われます。