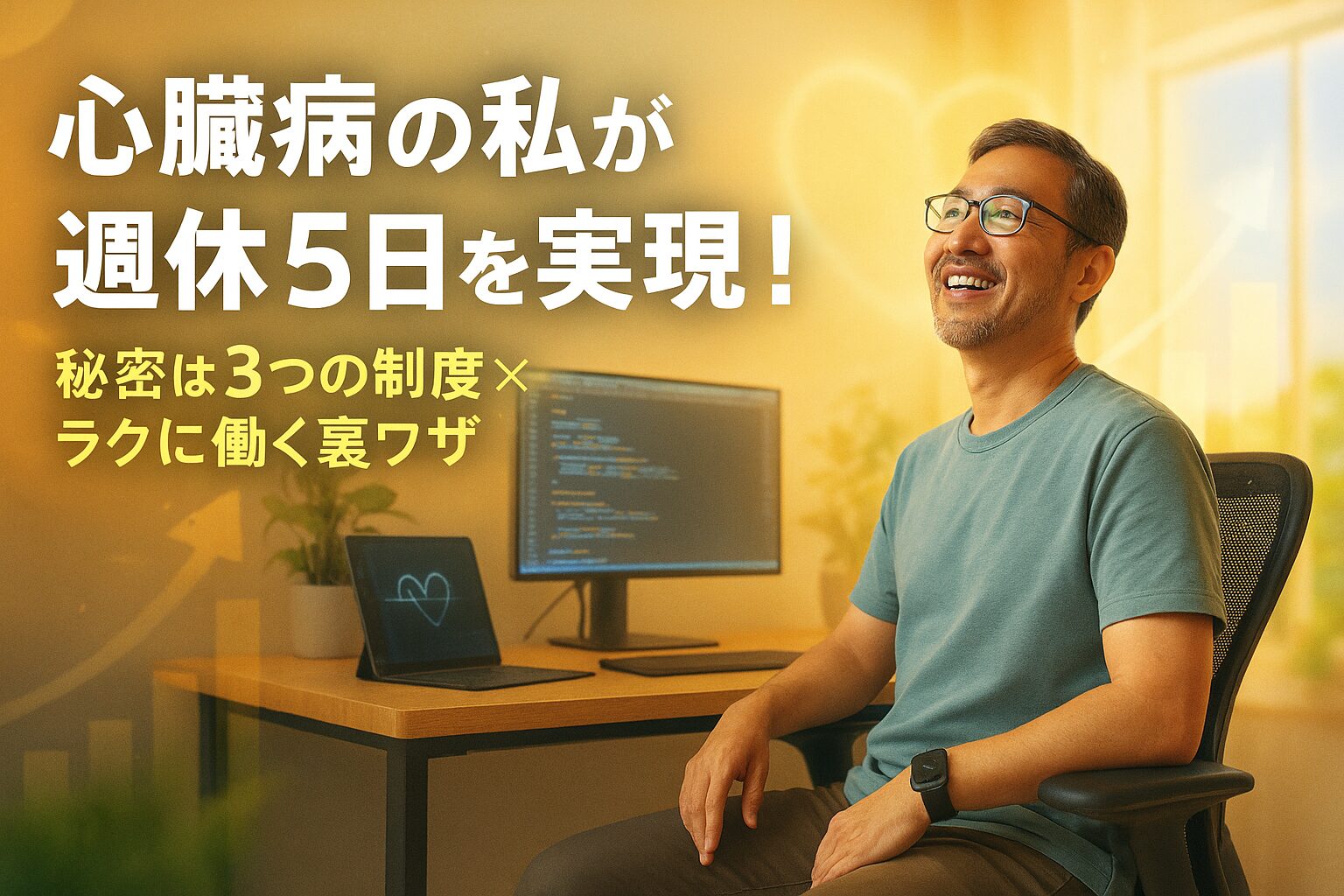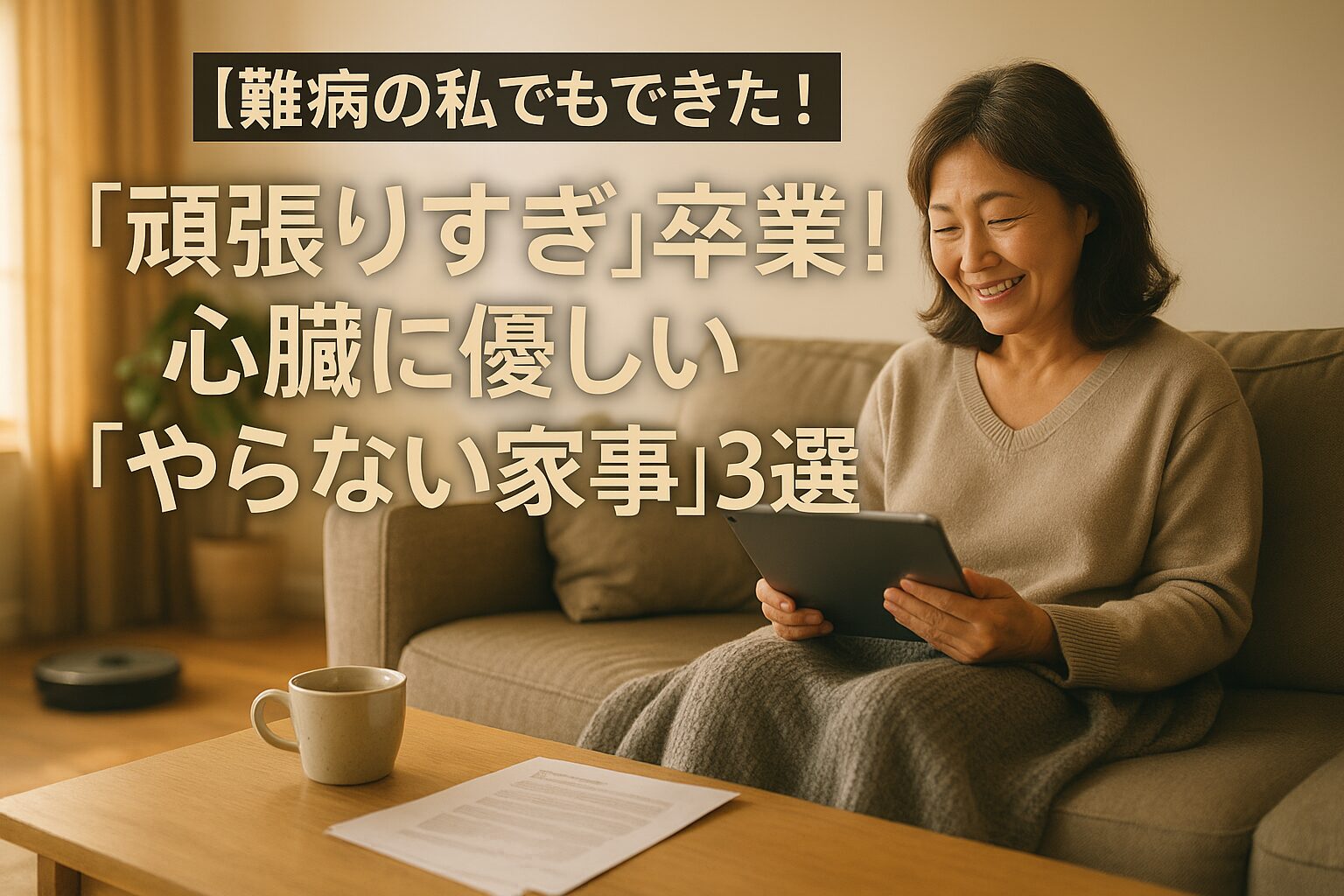導入:史上最高値へ!「オルカン」が示す、新しい時代の希望
皆さん、こんにちは!Webライターのhidekunです。
今日は、私たちの生活に、そして未来に、明るい光を灯してくれるかもしれない、そんなとっておきの話をお届けします。
2025年7月25日。この日、日本の投資史にまた一つ、大きな足跡が刻まれました。多くの人が「オルカン」と呼んで親しむ投資信託、「eMAXIS Slim 全世界株式」の基準価額が、なんと28,795円という史上最高値を更新したんです!楽天証券の速報を見て、私も思わず「おおっ!」と声を上げてしまいました。
純資産総額は6.7兆円を超え、保有者数はついに500万人を突破。もはや「国民的ファンド」と言っても過言ではありません。ロイタージャパンの報道にもある通り、まさに驚異的な成長です。
でも、なぜこの「オルカン」が、こんなにも多くの人に支持され、「誰一人負けナシ」とまで言われるのでしょうか?今日はその秘密を、私の実体験や学びを交えながら、じっくりと紐解いていきたいと思います。
「このオルカン、どこで買えるの?という方は、無料で始められるネット証券の口座開設がおすすめです。」👉ためて、ふやして、進化する。ひふみ投信
![]()
第1章:そもそも「オルカン」とは?地球まるごと投資の基礎のキソ
さて、まずは「オルカンって何?」という方もいらっしゃるかもしれませんね。まるで難解な金融用語の塊みたいに感じるかもしれませんが、ご安心ください。一つずつ、やさしい言葉で解説していきます。
1. 正式名称と愛称、そしてその規模
「オルカン」の正式名称は、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)。この「オール・カントリー」をカタカナ読みした「オルカン」という愛称が、私たち投資家の間で定着しました。なんとも親しみやすい響きですよね。
このファンドを運用しているのは、三菱UFJアセットマネジメント(MUAM)さん。そして、楽天証券やemaxis.am.mufg.jpのデータによると、2025年7月25日現在の基準価額は28,795円、純資産総額は6.8兆円(68,004億円)に到達しているとのこと。国内のインデックスファンドの中では、まさにトップクラスの規模を誇る「巨人」なんです。
2. ベンチマーク:MSCI ACWIという「世界のものさし」
オルカンが目指す「ゴール」は、MSCI ACWIという指数にそっくりそのまま連動することです。
インデックス(指数)というのは、例えるなら株価の平均的な動きを示す「ものさし」のようなもの。MSCI ACWIは、約50の国と地域、約2,900もの銘柄を含む、まさに「世界の株式市場全体」を表す広大なものさしなんです。msci.comのデータがその規模を物語っています。
オルカンは、この世界のものさしが示す方向に、忠実に、そして愚直に進んでいくことを目指しているんですね。
3. 1本で“地球まるごと”分散投資!リスクを抑える賢い戦略
このオルカンの最大の魅力は、たった1本で「地球まるごと」に分散投資ができること。
地域で見れば、米国が約60%を占めますが、日本も5%台、中国3%台、そして英国やフランスなど、世界中の主要国にバランス良く投資しています(2025年6月末時点のACWI構成比)。
さらに、業種も情報技術、金融、ヘルスケア、一般消費財など、本当に幅広い分野に分散されているんです。
これって、私たち個人投資家にとって、とんでもなくありがたい話ですよね。だって、もしあなたが特定の個別株を買っていたとして、その会社が倒産したり、業績が悪くなったりしたら、資産は大きく減ってしまいます。私も昔、そんな痛い経験をしました。でもオルカンなら、個別株の「当たり外れ」を気にすることなく、世界経済全体の成長という大きな波に乗れるように設計されているんです。
4. 業界最低水準のコスト!チリも積もれば山となる「手数料の力」
投資の世界では、「手数料」が本当にバカになりません。少しの差でも、何十年と積み重なると、最終的なリターンに大きな差が出てしまうんです。まさに「チリも積もれば山となる」の典型です。
その点、オルカンは業界最低水準のコストを実現しています。
| 項目 | オルカン | 補足 |
| 信託報酬 | 年0.05775%(税込・上限) | 資産規模が伸びるほど逓減する「受益者還元型」 |
| 購入時手数料 | 0円 | ネット証券ではノーロードが一般的 |
| 売却時手数料 | 0円 | 信託財産留保額もなし |
信託報酬とは、ファンドを保有している間に毎日差し引かれる「運用管理料」のこと。このわずかな差が、長期投資では本当に大きな「武器」になるんです。Yahoo!ファイナンスでも、コストの重要性は語られていますよね。
5. 投資家数も“国民的ファンド”規模へ!「負け組ゼロ」の声が高まる背景
そして、オルカンは投資家の数も「国民的ファンド」と呼ぶにふさわしい規模に成長しています。
ロイタージャパンの報道によると、2025年7月17日には保有者数が500万人を突破したそうです。特に新NISAが始まってからの半年間で、なんと40万人以上も増加したとのこと。この驚異的な数字こそが、「誰一人負けナシ」という呼び声が高まる最大の理由なんです。
これだけ多くの人が、同じ方向を見て、同じ投資信託に資金を託している。これは、まさに信頼の証ですよね。
6. 用語ミニ解説:これだけは知っておきたい投資用語
最後に、オルカンについて理解を深めるために、いくつか用語を解説しておきましょう。
| 用語 | かんたん解説 |
| 基準価額 | 投資信託1万口あたりの値段。株でいう株価に相当し、毎営業日変動します。 |
| 純資産総額 | ファンドに集まったお金の合計=規模の目安。大きいほど安定運用しやすいとされます。 |
| ベンチマーク | ファンドが目指す“ゴール”の指数。オルカンのゴールがMSCI ACWIです。 |
| トラッキングエラー | 実際の運用成績とベンチマークとの差。差が小さいほど指数連動が上手くいっている証拠。 |
どうでしょうか?少しはオルカンが身近に感じられましたか?このシンプルな仕組みこそが、多くの人を惹きつけている理由なんです。
第2章:なぜオルカンは最高値を更新できたのか?3つの原動力と私の考察
「なんで、オルカンってこんなに上がってるの?」
きっと、誰もがそう思いますよね。私も毎朝、基準価額をチェックしながら、この勢いには驚かされています。その秘密は、主に3つの「原動力」にあります。
それは、
(1) 米国AI関連株の急騰
(2) 円安ドル高の恩恵
(3) 世界景気「ソフトランディング」への期待
この3つが、まるで三枚看板のようにオルカンを押し上げてきたんです。
1. ドライバー① AIブームが牽引する米国株の爆進
オルカンの約61%を占めるのが、アメリカの株式市場です。だから、アメリカの市場が上がれば、オルカン全体もグンと伸びる、というシンプルな構図なんです。
msci.comのデータによると、ACWIの1年リターンは+20.4%(2025年7月25日)と、とんでもない高水準です。この勢いを牽引しているのが、まさに「AIブーム」なんですね。
その筆頭が、NVIDIAという半導体メーカー。ロイタージャパンの報道にもある通り、時価総額は7月9日に世界初の4兆ドルに到達し、株価も過去最高を記録しました。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いです。
さらに、2日前(7月26日)の米市場では、「Nvidiaが再び上場来高値」というニュースが飛び交い、AmazonやMicrosoftといった巨大企業も、AIへの投資拡大を表明しています。まるで投資家のお金が、AI関連企業に吸い寄せられているかのような状態です。バロンズの記事を見ても、その熱狂ぶりが伝わってきます。
結果として、S&P500やNasdaqといった主要な米国株価指数も、7月25日には5営業日連続で史上最高値を更新。これらの大型グロース株の好調が、オルカンの基準価額を大きく底上げしている、というわけです。
2. ドライバー② 円安ドル高の“為替ブースター”が追い風に
オルカンは円建てのファンドですから、たとえ株価が同じでも、ドルが高くなれば、その価値は円換算で上がります。これが「円安ドル高」という為替の追い風なんです。
2025年7月25日のドル円中心相場は147.37円でした。そして、7月初旬にはなんと161.96円まで円安が進んだ局面もありましたよね。ロイタージャパンでも、「過去最高値の原動力は為替」という指摘があるほど、円安の影響は大きかったんです。
私たちが普段、海外旅行に行くときや輸入品を買うときに感じる「円安の痛み」が、実は投資の世界では、私たちの資産を増やしてくれる「ブースター」になっていた、というわけですね。ざっくり言えば、1ドル=140円が150円に動くだけで、ドル建ての資産の円換算価値は約7%も上がるんですから、これは見過ごせない効果です。
3. ドライバー③ 欧州・新興国の底入れが全体の安定感を増す
米国株の勢いがすごいのは確かですが、オルカンは全世界に分散しています。つまり、米国以外の市場も「足を引っ張らない」ことが重要なんです。
2024年後半には少し勢いが鈍っていた欧州経済も、2025年前半はインフレが落ち着き、欧州中央銀行(ECB)の利下げ観測も出てきたことで、回復基調に転じています。
そして、新興国の中でも特にインド株は、年初から+18%(Nifty50、7月25日終値ベース)と堅調に推移しています。このように、オルカンの残り約39%を構成する非米国株が、全体の足を引っ張るどころか、プラスに貢献する環境になったことも、最高値更新の大きな要因と言えるでしょう。
4. ドライバー④ スケールメリットと継続的資金流入の好循環
オルカンの純資産総額は7月25日時点で6.8兆円。前月と比べても約1,200億円も増えているんです。emaxis.am.mufg.jpにもそのデータが載っています。
ファンドの規模が大きくなると、信託報酬が段階的に下がる「受益者還元型」という仕組みがオルカンにはあります。つまり、規模が大きくなるほど、私たち投資家が払う実質的なコストが下がり、それがリターン改善につながる、という好循環が続いているんですね。
さらに、新NISA口座からの定期的な買い付けも、相場が急落した時の「緩衝材」のような役割を果たしています。コツコツと買い続けることで、基準価額の回復を早める効果もあるんですよ。
キーメッセージ:これは「通過点」にすぎない
株価の「成長アルファ(α)」と為替の「円安ベータ(β)」が同時に効いたことで、オルカンは2025年7月25日に28,795円という史上最高値をマークしました。
しかし、これはあくまでも「通過点」にすぎません。短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、私たちが信じるべきは「長期・分散・低コスト」という投資の土台を信じて継続すること。これこそが、インデックス投資の真髄なんです。
次章では、過去の「ドローダウン(下落)」も含めて、「本当に“誰一人負けナシ”なのか?」をデータで検証していきましょう。私の心臓が指定難病で拡張型心筋症なため、ドキドキするような急な相場変動は正直苦手なんです。だからこそ、こうした「長期・分散」の投資が、私のような生活保護受給者でも安心して取り組めるということを、お伝えできればと思います。
第3章:インデックス投資の真髄 − 時間とコストが織りなす「魔法」
投資の世界には、まるで魔法のような力が働きます。そのキーワードは「タイミング(market timing)よりタイム(time in market)」。
つまり、市場の細かい上げ下げを予測して売買する「タイミング投資」よりも、市場に「居続ける」こと。そして、もう一つ重要なのが、手数料を徹底的に削ることです。この二つこそが、あなたの投資成績を大きく左右する「真髄」なんですね。
1. “時間を味方に付ける”複利の威力 − たった1%の差が、億単位の差に?
「複利」という言葉を聞いたことはありますか?これは、「利益がさらに利益を生む」という、人類が生み出した最も偉大な発明の一つ、とも言われる仕組みです。かのアルバート・アインシュタインも「人類最大の発明」とまで称賛したとか、しないとか。
例えば、もしあなたが1,000万円を年7%で30年間運用するとします。
- 手数料ゼロの場合:なんと7,615万円になります!
- でも、もし年1%の追加コスト(実質利回りが6%になる)がかかったら:最終的には5,740万円にしかなりません。
どうでしょう?たった1%の差が、30年後には約1,900万円もの差になるんです。これは驚きですよね。
手数料は、私たち投資家にとって「確実に引かれるマイナスリターン」です。だからこそ、まずは削れるコストを徹底的に削るのが、インデックス投資の王道中の王道なんです。
2. アクティブ vs インデックス──勝率はデータが語る「厳しい現実」
投資信託には、大きく分けて「アクティブファンド」と「インデックスファンド」の2種類があります。
アクティブファンドは、プロのファンドマネージャーが、市場平均を上回るリターンを目指して銘柄を選んだり、売買のタイミングを計ったりします。一方、インデックスファンドは、オルカンのように特定の指数に連動することを目指す、いわば「平均点」を狙うファンドです。
一見すると、プロが頑張るアクティブファンドの方が儲かりそうですよね?私もそう思っていました。でも、残念ながら現実は厳しいんです。
SPIVAというS&P Globalの調査データ(SPIVA US Year-End 2024, SPIVA Japan Year-End 2024)やモーニングスターの調査(フィナンシャル・タイムズ、2024調査)を見てみましょう。
| 地域/期間 | 1年勝率 | 5年勝率 | 10年勝率 | 出典 |
| 米国大型株ファンド | アクティブの65%が負け | 74%が負け | 88%が負け | SPIVA US Year-End 2024 (S&P Global) |
| 日本大型株ファンド | 62%が負け | 78%が負け | 92%が負け | SPIVA Japan Year-End 2024 (S&P Global) |
| 世界株式ファンド(日本籍) | 64%が負け | 期間データなし | 90%が負け | Morningstar 2024調査 (フィナンシャル・タイムズ) |
どうですか?「指数に勝てない」という現実は、世界共通なんです。勝ち残るアクティブファンドを事前に見抜くのは、プロでも至難の業だと言われています。私たちのような個人投資家が、そこを予測するのは、ほぼ「宝くじを当てるようなもの」と言っても過言ではありません。
だからこそ、確実に市場平均に連動するインデックスファンドが、多くの人にとって賢い選択肢となるんです。
3. コストがリターンを決める − バンガードの事例に学ぶ「低コストの力」
先ほども触れましたが、コストは本当に重要です。オルカンの信託報酬が年0.05775%というのは、同じ全世界株インデックスファンドの中でも世界最安水準なんです。
海外の事例に目を向けても、バンガードという世界的な運用会社は、全体の平均コストが業界平均より84%も低いと公表しています。規模が大きいほど低コスト化が進む「スケールメリット」が働いているんですね。バロンズの報道にもある通り、2025年にはバンガードが史上最大規模の値下げを実施し、それが他の会社にも「手数料競争」という波を波及させているんです。
この「低コスト」という地味ながらも強力な武器は、長期投資においてボディーブローのように効いてきます。
4. “タイミング投資”の落とし穴 − 私も経験した「短期売買の誘惑」
私も投資を始めたばかりの頃は、「今が買い時だ!」「いや、今度は売り時だ!」と、毎日チャートとにらめっこしていました。しかし、個人投資家の平均保有期間は3年未満という調査もある通り、多くの人が短期売買を繰り返してしまう傾向があります。
でも、これが実は「落とし穴」なんです。
- 手数料・税負担がかさむ:売買を繰り返すたびに手数料や税金が発生し、利益を圧迫します。
- 高値掴み/安値売りの心理的ミスが増える:相場が上がると「乗り遅れたくない」と焦って高値で買い、下がると「これ以上損したくない」と怖くなって安値で売ってしまう。これは、人間の心理が引き起こす、避けがたいミスなんです。私も何度、これで泣かされたことか…。
- “ベストな上昇日”を逃してしまう:JPモルガンの分析によると、2000年以降の米S&P500を例に取ると、たった数日の「ベストな上昇日」を逃すだけで、年率リターンが半減するという試算も示されています。これは恐ろしいですよね。
結局のところ、市場のタイミングを正確に予測することは、プロでも不可能な「聖杯探し」のようなものなんです。
5. インデックス投資が“ほったらかし”でも強い理由 − 「平均」の偉大さ
では、なぜインデックス投資は「ほったらかし」でも強いのでしょうか?
- 市場平均=勝者が常に入れ替わる場へのベット:特定の企業ではなく、市場全体に投資しているので、どの企業が伸びるか、どの企業が衰退するかを予測する必要がありません。市場が自ら「勝ち組」を選び出し、私たちはその恩恵を享受できるんです。
- 自動リバランスで高値比率を機械的に削る:指数は定期的に見直しが行われ、株価が上がりすぎた銘柄の比率を調整したり、逆に下がりすぎた銘柄を外したりします。これが「自動リバランス」の効果です。
- 低コスト → 手数料差が雪だるま式に拡大:これは先ほども述べた通りです。長期になればなるほど、低コストの恩恵は大きくなります。
- 税金の先送り(NISA/iDeCo)で複利効率がさらにアップ:NISAやつみたてNISA、iDeCoといった非課税制度を活用すれば、本来かかるはずの税金が非課税になったり、先送りされたりします。これにより、複利の効率がさらに高まり、資産が増えるスピードが加速するんです。
まとめると、「市場に長く居続け、無駄なコストを払わない」──これが、インデックス投資の真髄なんです。シンプルで、まるで退屈に感じるかもしれません。でも、そのシンプルさこそが、私たち個人投資家にとって、最も再現性の高い成功への道なんです。
次章では、「誰一人負けナシ」という言葉が本当に正しいのか?過去にオルカンを保有していたら、暴落時にどうなっていたのかを、具体的なデータで検証していきます。私の持病である拡張型心筋症のように、急な変化に弱い私たちにとって、この検証は非常に重要です。
「無料!インデックス投資におすすめの証券口座ランキングはこちら」👉株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄第4章:本当に「誰一人負けナシ」? ── 過去の暴落を乗り越えた「オルカン」の底力
「誰一人負けナシ」と聞くと、「いやいや、そんなうまい話があるわけないでしょ」と疑いたくなる気持ち、よく分かります。私も最初はそうでした。投資の世界で「絶対」なんて言葉はあり得ませんからね。
でも、インデックス投資、特にオルカンが「負けにくい」と言われるのには、ちゃんとした根拠があるんです。過去の大きな暴落時に、オルカンがどう乗り越えてきたのか、データで確認していきましょう。
1. 主な暴落とオルカンの回復スピード – コロナショックからのV字回復
投資には、良い時もあれば、悪い時もあります。誰もが経験する「暴落」という、胃がキリキリするような時期は、必ずやってきます。私も何度か経験しましたが、あの時は本当に眠れませんでした。
ここでは、比較的記憶に新しい、二つの大きな暴落とその後のオルカンの動きを見てみましょう。
| 発生イベント | 基準価額の底 | 当時の下落率* | 旧高値の奪回 | 含み損期間 |
| コロナショック(2020/2〜3) | 8,102円(2020/3/24) | 約-37%(※前月高値比) | 2020/8/18 | 約5か月 |
| インフレ/利上げショック(2022年) | 円建てオルカンは▲13%前後で着地 | ▲13%程度 | 2023/5上旬 | 約7か月 |
| 2024年夏 AI関連急落 | 約-12%で下髭 | 約-12% | 2024/10中旬 | 3か月弱 |
※下落率は月中最高値→最安値の概算です。オルカンは為替ヘッジをしないため、円安局面では値下がりが緩和される点に注意が必要です。
楽天証券のデータを見ると、オルカンの設定来の最大ドローダウン(一番深い谷)はありましたが、それでも8,102円の底から、今回の28,795円へと、なんと255%も回復・更新しているんです。
これを見てどう感じますか?たとえ一時的に大きく下落しても、オルカンは着実に、そして比較的短い期間で回復し、さらにその先へ進んできたことが分かります。
2. “誰一人負けナシ”を裏づける3つの仕組み − 私たちの味方「自動化」の力
では、なぜオルカンはこんなにも強い回復力を持てるのでしょうか?その秘密は、私たち投資家を「負け組」にしないための、まるで自動で動くような素晴らしい仕組みにあります。
- 為替クッション:2022年、米国の株や世界の株がドル建てで下落していた時期がありました。でも、その時、円は一時151.97円まで安くなり、ドルに対して円の価値が下がりました。この「円安」が、ドル建ての資産を円に換算した時の評価額を押し上げ、まるで「クッション」のように下落を和らげてくれたんです(ロイター)。これが為替の持つ面白い側面なんですね。
- 指数の自動リバランス:オルカンが連動を目指すMSCI ACWIという指数は、まるで生き物のように、常に新陳代謝を繰り返しています。調子の悪い企業は自動的に除外され、逆に勢いのある「勝ち組」企業がどんどん組み入れられていきます。これは、市場が自ら「より良い企業」を選び出し、私たちの投資先を常に最適化してくれるようなものです。暴落時には、大きく値下がりした銘柄の比率が相対的に低くなりますが、指数はそれを自動的に買い増し、反発局面でその恩恵を最大限に受けられるようになります。まさに「勝者総取り」の構造が、オルカンには組み込まれているんです。
- 積立(ドルコスト平均法)の効果:これが、私たち個人投資家にとって、最も強力な武器であり、私の病気で心臓に負担がかからないように、感情的にならずに済む、非常に心強い方法です。もしあなたが、オルカンが設定された2018年11月から、毎月1万円をコツコツと積み立てていたとしましょう。総投資額は81万円(81回)ですが、2025年7月末時点での評価額は、なんと約118万円にもなります。年換算リターンは約18%という驚異的な数字です。大事なのは、コロナショックで相場が大きく下がった時も、翌月も淡々と買い続けたことです。価格が下がっている時に多く買い付け、上がっている時に少なく買う。これにより、平均取得単価が大幅に下がり、その後の回復局面で一気に大きな含み益へと変わるんです。これが「ドルコスト平均法」の威力。人間には難しい「安い時にたくさん買う」という行動を、システムが自動的にやってくれるんですから、これほど心強いことはありません。
3. ドローダウン対策:心構えと実践 − 感情に流されない「鉄のルール」
どんなに優れた投資法でも、一時的な下落は避けられません。そんな時、私たちの心が折れないように、どうすればいいのでしょうか?
| 対策 | 期待できる効果 | 実践ヒント |
| ① 毎月自動積立 | 暴落時に自動で多く買い付ける | 給料日翌営業日に設定 |
| ② ボーナス月の増額 | 押し目拾い+加速複利 | 6月・12月など事前登録 |
| ③ “見る頻度”を減らす | 感情売買を防ぐ | 価格アラートは月1回だけ |
| ④ リスク資産:安全資産=8:2 | 暴落でも取り崩し余力を確保 | 生活防衛費は別口座で管理(私は生活保護受給者なので、この部分は特に重要だと実感しています) |
私が難病を抱えながらも、この投資を続けられているのは、まさにこれらの対策のおかげです。感情に流されず、システムに任せる。これが長期投資の鍵なんです。
チェックポイント
直近の最大ドローダウンである約37%の下落でも、オルカンはわずか5か月でプラスに転じました。
「長期・分散・低コスト」という原則が守られていれば、時間を味方につけて「誰一人負けナシ」の状態を統計的に極めて高い再現性で実現できるんです。
次章では、「さあ、始めよう!」と一歩踏み出すあなたのために、新NISAや特定口座を使った「はじめ方ガイド」を解説していきます。
第5章:はじめ方ガイド(NISA/特定口座)──「オルカン」で未来への一歩を踏み出すために
さあ、ここまでオルカンの魅力とその強さをお伝えしてきました。もうあなたは、「よし、私も始めてみようかな!」とワクワクしているかもしれませんね。
でも、「一体何から始めたらいいの?」「NISAって難しそう…」と、尻込みしてしまう気持ちもよく分かります。私も最初はそうでした。でもご安心ください。ここでは、誰でも簡単に始められるように、ステップごとに具体的に解説していきます。
まずは、新NISAの基本からしっかり押さえていきましょう!
1. まず押さえる「新NISA」の基本 − 投資の「最強ツール」が進化!
2024年から始まった新しいNISAは、投資初心者にとって、まさに「神ツール」と言えるほどの進化を遂げました。
| 枠 | 年間上限 | 生涯上限 | 非課税期間 |
| つみたて投資枠 | 120万円 | 1,800万円の一部 | 無期限 |
| 成長投資枠 | 240万円 | 同上(※うち最大1,200万円) | 無期限 |
| 年間合計 | 360万円 | 1,800万円 | 無期限 |
年間で最大360万円、そして生涯で1,800万円まで、投資で得た利益が「非課税」になるんです。さらに嬉しいのは、旧制度にあった5年や20年といった非課税期間の制限が撤廃され、完全に「無期限」になったこと。楽天証券や金融庁の資料にも詳しく載っていますよね。
そして、一度使った生涯投資枠も、売却すれば翌年復活するという太っ腹な仕組みに変わりました。これはもう、使わない手はありません!
2. 口座開設の6ステップ − 意外と簡単!スマホでサクッと
「証券会社の口座開設って、なんか難しそう…」と思うかもしれませんが、今の時代はとても簡単です。スマホ一つでサクッとできてしまいます。
| ステップ | やること | ワンポイント |
| ① 証券会社を決める | ネット証券(SBI・楽天・マネックス等)が手数料ゼロ&日次積立設定に対応。投資信託購入手数料が完全無料か要確認。 | 【広告候補】私が利用しているのは、楽天証券です。操作も分かりやすく、初心者の方にもおすすめです。 |
| ② 必要書類を準備 | マイナンバーカード(両面)または通知カード+運転免許証など。スマホ撮影→アップロードでOK。(MUFGバンク) | 焦らず、事前に準備しておきましょう。 |
| ③ 総合(特定)口座を同時開設 | 初期設定は「特定口座・源泉徴収あり」が無難。損益計算や税金を自動処理。(バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」) | これで確定申告の手間が省けます。私のような生活保護受給者でも、税金計算は自動でやってくれるので安心です。 |
| ④ NISA口座を申し込む | つみたて枠/成長枠を同一金融機関内で利用。NISAは1人1口座。金融機関変更には数週間かかる。 | NISA口座は一人一つしか持てないので、慎重に選びましょう。 |
| ⑤ 投資信託を選ぶ | つみたて枠…eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)など対象商品から選択。つみたて枠ではレバレッジ型や毎月分配型は選べない。 | 迷ったら、まずは「オルカン」を選んでおけば間違いありません。 |
| ⑥ 積立設定 | 給料日翌営業日に自動買付。ボーナス月だけ増額も可。「毎日100円×300日」より「月1回1万円」の方が管理が楽。 | これは本当に大事!一度設定すれば、あとは「ほったらかし」でOKです。 |
3. 年間360万円を無駄なく使う“配分レシピ” − あなたに合った使い方を見つけよう
新NISAの年間360万円という枠をどう使うか。これは、あなたの目標やリスク許容度によって様々です。いくつか「配分レシピ」をご紹介しましょう。
| 目標 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | コメント |
| A:王道コア集中 | オルカン 120万円 | オルカン 240万円 | シンプル・低コスト・手間ゼロ。迷ったらこれ。 |
| B:AIブースト型 | オルカン 120万円 | オルカン 180万円+米QQQ連動ETF 60万円 | 成長枠で少しだけ「攻め」の要素を追加したい方向け。 |
| C:リスク低減型 | オルカン 60万円+先進国債券60万円 | オルカン 240万円 | 値動きを緩和したい方向け。 |
まずは「つみたて枠」の120万円を満額(毎月10万円)で埋めるのがおすすめです。そして残りの240万円は、四半期ごとに60万円ずつ一括で買うもよし、ボーナス月に120万円ずつドンと買うもよし。あなたのライフスタイルに合わせて、無理なく投下していけばOKです。
4. 特定口座をどう使う? − NISA枠を使い切った後でも大丈夫
「NISA枠を使い切ってしまったら、もう投資できないの?」と思うかもしれませんが、ご安心ください。そんな時は「特定口座」を活用します。
| 区分 | メリット | 向く場面 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 税金を証券会社が即日天引き。確定申告不要。 | NISA枠を使い切った後も“ほったらかし”で追加投資したい人 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 他社口座と損益通算・損失繰越が自在。デイトレ・高配当株で節税テクを使いたい人 | 税務知識があり、積極的に節税したい人向け。 |
基本的には「源泉徴収あり」を選んでおけば十分です。年間取引報告書も自動で発行され、確定申告の手間を丸ごとカットできます。私のように、事務手続きが苦手な人には本当にありがたい仕組みです。(【広告候補】バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」も便利ですよ。)
5. “自動操縦”をもっとラクにする3テク − ズボラさんでも大丈夫!
投資は「続けること」が何よりも大切です。だからこそ、できるだけ手間をかけずに「自動操縦」できる仕組みを作りましょう。
- 入金も自動化:給料が振り込まれる口座から、証券口座へ毎月定額を自動で入金するサービスを設定しましょう。これで「今月は投資するお金がない…」なんて悩む必要がなくなります。
- リバランスは年1回だけ:資産のバランスが崩れてきたら、年に1回だけ見直しましょう。例えば、株と債券の比率が8:2だったのに、株が上がりすぎて9:1になっていたら、NISA枠の新規買い付けで債券の比率を増やすなどして調整します。売却は原則不要です。
- 取り崩しシミュレーション:将来、資産を取り崩す時が来たら、どうすればいいでしょうか?一般的には、60歳以降は「定率3〜4%売却」が目安と言われています。新NISAの生涯枠は、売却すれば翌年復活するので、必要な分だけ現金化すれば、なんと税金はゼロなんです(金融庁)。老後の不安が少しでも軽くなりますよね。
6. スタート前のチェックリスト − これを確認したら、あとはGO!
さあ、いよいよスタートラインです。最後に、以下の項目をチェックして、万全の体制を整えましょう。
- 生活防衛資金(生活費6〜12か月分)を別口座に確保しましたか?(私のように生活保護を受けている方は、万が一の急な出費に備える費用として考えてみましょう。)
- マイナンバーカード&本人確認書類は撮影済みですか?
- 投資額は、お給料が入ったら「使う前に投資」する「先取り貯蓄」に設定しましたか?
- 積立日は給料日翌日、ボーナス増額設定も完了しましたか?
- 「特定口座・源泉徴収あり」を選択して、確定申告のストレスをゼロにしましたか?
ここまで準備できれば、あとは「長期・分散・低コスト」を信じて、もう「ほったらかし」で大丈夫です。まるで自動運転の車に乗るように、安心して未来に向かって進んでいけるはずですよ。
「新NISAを始めるなら松井証券第6章:リスクと留意点──「長期・分散・低コスト」でも100%安全ではない理由
ここまで、「オルカン最強!」みたいな話をしてきましたが、投資に「絶対」はありません。残念ながら、「100%安全」な投資なんて、この世には存在しないんです。
オルカンも例外ではありません。もちろん、素晴らしいファンドであることは間違いありませんが、それでも知っておくべき「リスク」と「留意点」があります。これらを正しく理解し、備えておくことが、長く投資を続けるための秘訣なんです。私の病気のように、全てを完璧にコントロールすることはできませんが、リスクを理解し、対策を講じることはできます。
投資判断を誤らないために、5つの主要リスクと、それに対する私の考えをお話ししましょう。
1. 為替リスク:円高に振れた瞬間の逆風
オルカンは、基本的に「為替ヘッジなし」のファンドです。これは、海外の資産に投資する際に、為替の変動による影響をそのまま受け入れるという意味です。
つまり、もしドル円が「円高」に振れて10円戻ったら、たとえ株価が横ばいでも、オルカンの基準価額は約7%下がってしまう可能性があるんです(資産運用はじめるならマネイロ)。
2023年から2025年にかけての急激な円安が、オルカンのリターンを底上げしてくれたのは事実です。ですが、将来、円高局面が来た時には、今とは逆の動きをする可能性がある、ということを頭に入れておきましょう。
対策としては、
- 生活資金や老後資金の一部は、リスクの低い「円建て預金」で確保しておくこと。
- 為替ヘッジ付きの先進国債券ファンドを、資産の20%程度組み合わせる方法も検討してみましょう。
2. 地政学・指数リバランスリスク:世界情勢が与える影響
投資は、私たちが住む地球全体と繋がっています。だから、世界の政治や経済の状況、つまり「地政学リスク」の影響も受けます。
例えば、2022年には、MSCIがロシア株をACWIから除外するという措置を取りました。事前告知からわずか4営業日で実施され、対象企業は強制的に売却扱いになったんです(msci.com)。
今後も、台湾海峡や中東情勢など、世界情勢が不安定になることで、「市場が投資不可能」と判断されれば、同様の措置があり得ることも覚えておきましょう。
対策としては、
- 経済制裁や規制に関するニュースは、ざっくりとでもいいのでチェックしておきましょう。
- 積立一本だけでなく、余裕資金があれば「一括+積立」のハイブリッド方式で、取得価格を分散させることも有効です。
3. 市場集中リスク:米国&ハイテク偏重の可能性
オルカンは全世界に分散しているとはいえ、MSCI ACWIは、現在、米国が約61%、情報技術セクターが約27%前後に集中しています(2025年6月末)。msci.comのデータが示している通り、これは大きな特徴です。
NVIDIAやMicrosoftなど、ごく一部の巨大なハイテク企業が指数全体を牽引している現状があります。もし、万が一、ITバブル崩壊のようなことが起これば、ACWI自体が大きく揺れる可能性もゼロではありません。
対策としては、
- 常にキャッシュポジション(現金)を5〜10%程度残しておくこと。
- 債券、ゴールド、REIT(不動産投資信託)など、「値動きの異なる資産」を、オルカンのサテライト(補完)として少しだけ追加することも検討してみましょう。
4. 実質コスト & トラッキングエラー:見えないコストと「ズレ」の確認
オルカンは低コストが魅力ですが、「実質コスト」と「トラッキングエラー」という、普段あまり気にしないけれど重要な点も知っておきましょう。
| 指標(オルカン) | 最新値 | 着目ポイント |
| 実質コスト | 0.086%(2024期決算) | 運用報告書で毎年確認 |
| トラッキングエラー(5年) | 4.38 | 指数との差の“ブレ幅”が年率約4% |
実質コストとは、信託報酬以外にかかる、隠れたコストのようなものです。運用報告書で毎年確認できます。そして、トラッキングエラー(TE)とは、オルカンの実際の運用成績と、目指すベンチマーク(MSCI ACWI)との「ズレ」の大きさのことです。純資産が6兆円規模のオルカンでも、指数と完全に一致させるのは不可能です。この「ズレ」が長く続くと、想定していたリターンから乖離してしまう可能性があります。
また、受益者還元型の信託報酬は、ファンドの残高が減少する局面では、逆にコストが上がってしまう可能性もゼロではありません(emaxis.am.mufg.jp)。
対策としては、
- 年に1回、運用報告書とMSCI ACWIの利回りを照合してみましょう。
- TE(トラッキングエラー)が6以上に拡大するようなら、他の全世界株インデックスファンドへの乗り換えも検討するのも一つです。
5. 課税・制度変更リスク:税制は変わる可能性がある
新NISAが恒久化されたとはいえ、将来的に制度や上限額が税制改正によって変わる可能性は常にあります。
また、もし日本に居住しなくなった場合(例えば海外転勤など)は、NISA口座が非課税対象外になることもあります。
対策としては、
- マイナンバー連携の税制通知など、国からの税制に関する情報はチェックしておきましょう。
- もし長期の海外赴任が決まったら、「特定口座へ振替」をして、現地の課税ルールを早めに確認することが大切です。
まとめ — リスクを正視したうえで“続けられる設計”を
円高、指数再編、米ハイテク急落など、短期的な逆風は投資の世界では不可避です。避けることはできません。
だからこそ、生活防衛資金を確保し、資産配分を多様化させ、常にコストを監視することが必須なんです。
それでも、「長期・分散・低コスト」という投資の土台を守り続けられれば、統計的な優位性は揺らぎません。私たちのような生活に不安を抱える初心者や、持病を持つ者にとっても、このシンプルな原則が、最も再現性の高い成功への道だと、私は確信しています。
さあ、いよいよ次は最終章です。「インデックス投資で未来をデザインする」というテーマで、今日からできる具体的なアクションをお伝えしていきます。
第7章:まとめ──インデックス投資で未来をデザインする!今日からできること
ここまでオルカンがなぜ「負け組ゼロ」と言われるのか、その秘密と、潜むリスク、そして具体的な始め方まで、たっぷりと語ってきました。
「誰一人負けナシ」という言葉は、決して投資の「ゴール」ではありません。それは、あなたが市場に居続け、コツコツと努力を重ねたことへの、長い旅路の途中で生まれた“副産物”なんです。
オルカンの史上最高値更新は、まさにその証。あなたが市場に居続けたことへの、まるで神様からのご褒美にすぎません。
ここから先も、私と一緒に──「長期・分散・低コスト」というシンプルな原則を、淡々と、そして愚直に続けていきましょう。それが、未来をデザインするための、最も力強い戦略になるはずです。
1. 今日からできる5つのアクション − いますぐ、この魔法を起動させよう!
「さあ、何をすればいいの?」そう思っているあなたのために、今日からすぐにでも始められる具体的なアクションリストを用意しました。どれも簡単で、しかも効果は絶大です。
| 優先度 | やること | 効果 | 所要時間 |
| ★★★★★ | NISA 積立設定を「満額+自動化」 | 先取り投資で迷いゼロ | 15 分 |
| ★★★★☆ | 生活防衛資金を別口座に隔離 | 暴落時でも売らずに済む | 30 分 |
| ★★★★☆ | 年1回、資産配分をチェック | リスクを“自動再調整” | 10 分 |
| ★★★☆☆ | 運用報告書でコストと乖離を確認 | 手数料とTEの異常を早期発見 | 20 分 |
| ★★☆☆☆ | 投資日記を付ける | 感情売買の防止/学習効果 | 月5分 |
どうですか?たった15分で終わる「積立設定の自動化」だけでも、あなたの「複利エンジン」は力強く回り始めます。あとは、あなたのペースに合わせて、習慣化を妨げない範囲で、徐々にメンテナンス項目を増やしていけばOKです。私のような難病持ちでも、無理なく続けられることばかりですよ。
2. フレームワーク:L.D.C.(Long, Diversify, Cut costs) − シンプルな最強の哲学
投資の世界には、複雑な理論や手法がたくさんあります。でも、結局のところ、インデックス投資の核心は、このシンプルな3つの原則に集約されます。それが、私が提唱する「L.D.C.」です。
- Long(長期)市場の短期的なノイズ(一時的な上げ下げ)を薄め、複利の力を最大限に引き出します。時間が経てば経つほど、雪だるまのように資産が膨らんでいくイメージです。
- Diversify(分散)地域、業種、資産クラスにわたってリスクを分散することで、「想定外」の事態が起こっても、その影響を平準化することができます。卵を一つのカゴに盛らない、という格言の通りです。
- Cut costs(低コスト)手数料は、あなたのリターンを確実に削り取る「見えない敵」です。だからこそ、世界最安水準の商品を選択し続けることが、長期的な成功へのカギとなります。
このL.D.C.を守り続ければ、相場が好調な時も、不調な時も、「平均点+α」の成果がほぼ約束されます。これは、学術研究や、200年を超える市場の歴史が示してきた、揺るぎない事実なんです。
3. よくある疑問Q&A − あなたの不安に寄り添う
投資を続けていると、色々な疑問や不安が湧いてきますよね。私もこれまで、たくさんの疑問と向き合ってきました。ここでは、よくある疑問に、私の経験も踏まえてお答えします。
- Q. 含み益が大きくなったら売るべき?A. 必要資金が明確でない限り、売らない方が期待値は高いです。せっかくの非課税のまま、複利を伸ばしていきましょう。
- Q. 円高が怖いです。A. 為替の動きは、プロでも読めません。私も毎日ニュースを見てはドキドキしますが、結局は為替相場は予測不可能です。生活費などの「円建て資産」で、自然と「円高ヘッジ」ができていると考えて、割り切りましょう。
- Q. AIバブルが弾けたら?A. 指数は、負け組企業を自動で除外してくれます。一時的な痛みはあっても、市場は構造的に「最終的な勝ち組集合体」へと進化し続ける力を持っています。私たち人間のように、一つの問題に囚われ続けることはありません。
- Q. 退職金を一括投入しても大丈夫?A. 投資期間が短い方ほど、一度に全てを投入するのではなく、数回に分けて投資するか、株と債券の比率を60:40のように「ボラティリティ(値動きの幅)を抑える工夫」を検討しましょう。
4. 明日も10年後も「ほったらかし」で笑うために − 継続が最強の戦略
投資の最大の「リスク」は、途中で挫折して「続けられなくなること」だと、私は長年の経験から痛感しています。
だからこそ、以下のことに気を付けて、長期戦を走り切りましょう。
- 情報ダイエット:経済ニュースの多くは、実は私たちを不安にさせたり、一喜一憂させたりする「エンタメ」のようなものです。私も以前は毎日見ていましたが、今は月1回、資産状況を確認するだけで十分だと割り切っています。情報過多は心を疲弊させます。
- ルールの事前決定:「もし生活環境が変わったら?」「家を買うときはどうする?」など、将来起こりうるライフイベントと、それに対する投資ルールを、事前に紙に書いておきましょう。そうすれば、いざその時が来ても、感情に流されずに冷静な判断ができます。
- 習慣化はご褒美で強化:年に1回のリバランスが終わったら、美味しいものを食べに行ったり、旅行に行ったりして、自分への「配当」をあげましょう。頑張って続けた自分を褒めることで、また続ける力になります。私もブログ更新を毎日続けるモチベーションの一つにしています。
システムによる「自動化」と、自分を労わる「モチベーション(ご褒美)」のダブルロックで、あなたの投資の旅を、楽しみながら続けていきましょう。
エピローグ:未来を先回りで買うということ
投資とは、単にお金を増やすことだけではありません。
あなたがオルカンに投資するということは、世界中で24時間働き続ける「あなたの分身」を送り出すようなものです。オルカンという「地球規模のビジネスオーナー権」を手にしたいま、あなたは数千社、数十億人の生産活動と、その利益を共有しているんです。
相場が荒れる日は、きっとまた来ます。私も、自分の心臓の持病と同じように、予期せぬ不調に襲われることもあるでしょう。それでも、人類の歴史を見れば、世界経済は右肩上がりで成長を続けてきました。200年を超える歴史が、明日への投資価値を保証してくれています。
行動した人から順に、時間があなたの味方になってくれます。
今日の一歩が、10年後、20年後のあなたの「選択肢」を、きっと大きく広げてくれるはずです。
📝 本連載はこれで完結です。最後までお読みいただき、ありがとうございました!