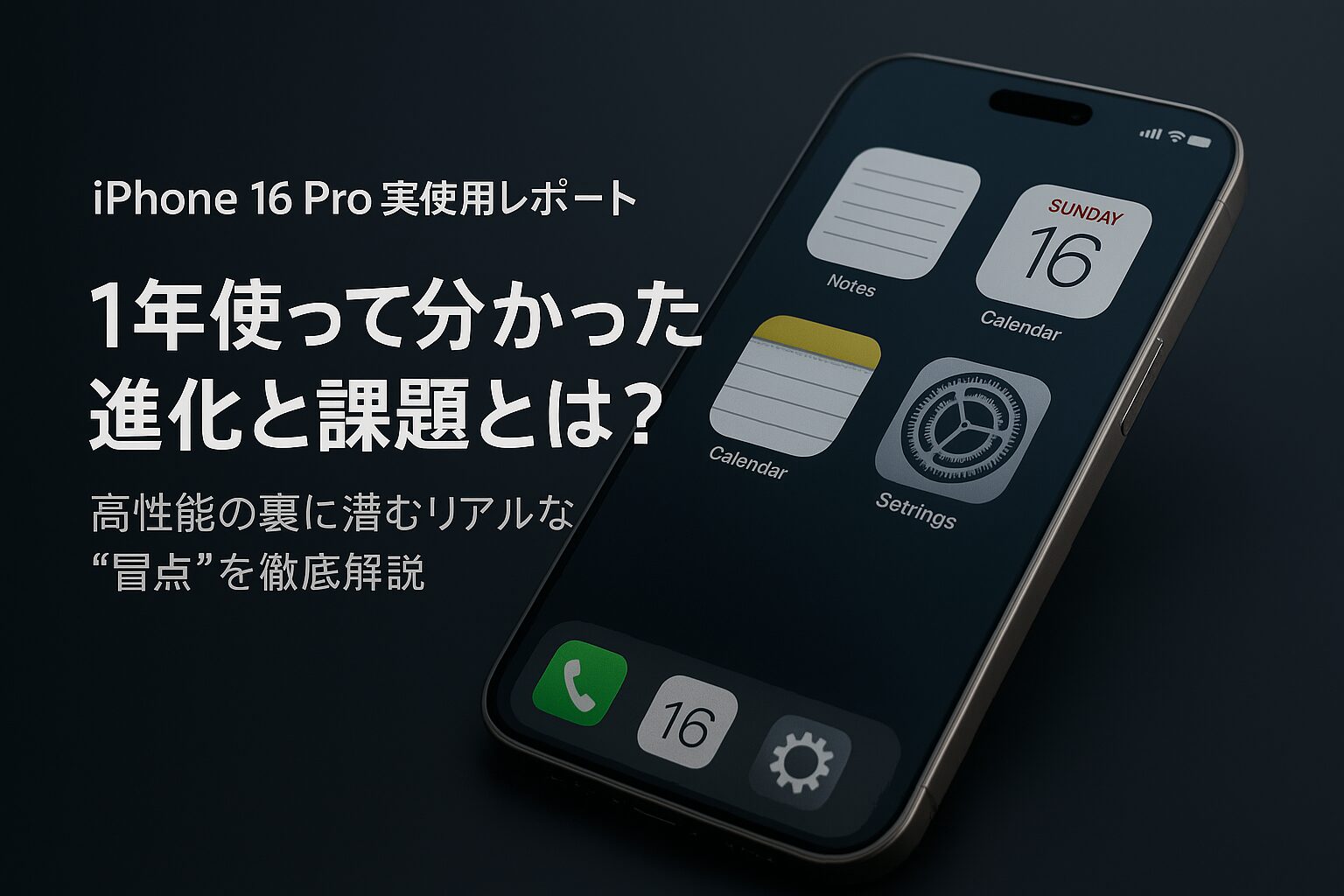第1章:価格決めの基本的な2つの方法
ビジネスを始めたとき、まず悩むのが「いくらで売るか?」という点です。これはどんな規模の事業者にとっても大切なテーマですが、特に副業や個人事業主、フリーランスにとっては死活問題とも言えます。
価格を決める方法として、基本的には以下の2つがあります。
① 原価+欲しい利益
これは最もシンプルで論理的な方法です。たとえば、あなたがハンドメイドでアクセサリーを作っているとしましょう。
- 材料費:500円
- 製作時間:2時間
この場合、単に材料費を元にして300円で売ってしまえば、「原価割れ」です。つまり、作れば作るほど赤字になる構造です。こんなことでは、ビジネスの持続は不可能ですし、発展の余地もゼロです。
価格設定の基本はこうです。
原価(材料費+労力コスト)+欲しい利益 = 売値
例えば
- 材料費:500円
- 労力コスト(時給1,000円×2時間):2,000円
- 合計原価:2,500円
- 利益:500円
- 売値:3,000円
このように、ちゃんと自分の時間や労力も「コスト」として扱うことが大切です。
ただし、「欲しい利益」をいくらにするべきか分からないという声もよく聞きます。ビジネス慣れしていないうちは、妥当な利益を見極めるのが難しいのも事実です。
そんなときに使えるのが、次の方法です。
② 人気商品と同じ価格にする
こちらは、既に市場で成功している商品やサービスの価格をベンチマーク(参考)にする方法です。たとえば
- 近所の人気美容室のカットが5,500円なら、自分も同じ価格で設定する
- 投資系の人気noteが月額500円なら、自分も同額にする
これは「価格の相場感」を理解し、失敗を避けるための実践的な方法です。人気商品は、それ以上高くしても売れず、安くしても利益が出ない「最適価格」に落ち着いている可能性が高いのです。
ただし注意が必要なのは、「マネする対象を間違えないこと」。売れていない商品や大企業の大量生産商品などは参考になりません。あくまで、自分と同じような規模の成功しているスモールビジネスの価格を参考にしましょう。
この2つの方法をうまく使い分けることで、価格決めの迷いは大きく減ります。次章では、「人気商品の価格設定の見極め方」について、さらに具体的に掘り下げていきましょう。
無料の会計自動化ソフト マネーフォワード クラウド会計第2章:価格の参考にするべき「人気商品」とは?
「人気商品の価格を参考にしよう」と言われても、実はここでつまずく人が非常に多いです。というのも、「人気」と「利益が出ている」はイコールではないからです。
表面的に「売れている=儲かっている」と思いがちですが、実際はそんなに単純な話ではありません。ここでは、人気商品の正しい見極め方と、その裏にある価格戦略について見ていきましょう。
「売れてる商品=儲かる商品」ではない
たとえば、マクドナルドの戦略が良い例です。
- ハンバーガーは安く提供し、たくさん広告を打って集客
- 実は利益が出ているのは、コーラやポテトなどのドリンク・サイドメニュー
これは「集客商品(フロントエンド)」と「収益商品(バックエンド)」を分けて考える戦略です。つまり、お客さんを引きつけるために利益度外視で提供している商品と、しっかり利益を出すための商品が存在しているということ。
この戦略を知らずに、「あの商品が人気だから、同じ価格で真似しよう!」と安易にマネしてしまうと…
- 原価に見合わない価格設定
- 時給換算すると超薄利
- 売れても売れても儲からない
といった“地獄”に陥る可能性があります。
フロントエンド商品とバックエンド商品
マーケティングでは、以下のように商品を分類します
- フロントエンド商品:初めてのお客さんに届ける、安価でハードルの低い商品。客寄せの役割を果たす。
- バックエンド商品:信頼関係ができた後に販売する、高価格で利益率の高い商品。ここで収益をしっかり取る。
あなたがマネしようとしている「人気商品」が、フロントエンド商品だった場合、その価格を参考にしても意味がないのです。
例えば、
- 無料お試し
- 初回限定500円
- 月額100円キャンペーン
といったサービスは、フロントエンド商品です。これは“儲けるため”ではなく、“お客さんを獲得するため”の価格設定。
これを真似して同じような価格で売っても、あなたにはマクドナルドのような規模のバックエンド商品や仕組みがないため、利益を出すことができません。
じゃあ、どの価格をマネすれば良いの?
以下のポイントを意識しましょう
- スモールビジネスで成功している人の価格を参考にする
- 「それ一本で収益を出している商品」の価格をベースにする
- バックエンド商品まで含めた価格構造を分析する
特に同じジャンル・同じ顧客層に向けてビジネスしている「個人起業家」「フリーランス」「副業プレイヤー」の価格設定は、あなたのビジネスにも応用が効きやすいです。
その上で、競合より「高い価格」「低い価格」に設定する場合は、必ず理由と根拠が必要です。
- 高い価格にする → より高い付加価値がある
- 安い価格にする → 圧倒的なコストカットができる
このようにして、価格設定に“説得力”を持たせることが、持続可能で利益の出るビジネスには不可欠です。
第3章:失敗しない値付けの鉄則
価格を決めるとき、「利益を出すこと」だけを考えると、どうしても全ての商品にしっかり利益を乗せたくなります。でもそれが、かえってお客さんを遠ざけてしまうこともあります。
ここでは、「価格決めで絶対にやってはいけないこと」と「成功する値付けの原則」について詳しく解説していきます。
フロントエンド商品は絶対に高くしてはいけない
フロントエンド商品とは、新規のお客さんが最初に出会う商品やサービスのことです。これはあくまで「信頼関係をつくる入口」であり、「儲けるための出口」ではありません。
ところが、ここに高い価格をつけてしまう人が多いのです。
なぜでしょうか?
- 自分の商品に自信がある
- 時間や労力をかけたから、しっかり利益を取りたい
- 安売りしたくないというプライド
こうした思いは分かります。しかし、これをやってしまうと…
お客さんが入口でつまづく=誰も買ってくれないという悲惨な結果になります。
現実を見てください。
- 初回限定〇〇%オフ
- 今だけ無料お試し
- 初月100円キャンペーン
こうした“安くてお得なオファー”が世の中にあふれている理由は何か?
それは、「お客さんにまず試してもらうこと」がビジネスの第一歩だからです。
高い商品をいきなり売るのは、信頼関係ゼロの状態ではほぼ不可能。だからこそ、フロントエンド商品はとにかく“買ってもらいやすい価格”にする必要があるんです。
原価割れでもOK?実は正解の場合もある
「えっ!?赤字になっちゃうじゃん」と思ったあなた。確かに、単体で見ればフロントエンド商品は利益が出ないこともあります。でも、それでOKなのです。
理由は明確:
フロントエンド商品でお客さんの信頼を得て、バックエンド商品で利益を出す。
この流れがあってこそ、ビジネスは回ります。
極端な話、フロントエンド商品は“原価割れ”でもいい。無料でもいい。 重要なのは、その後に続くバックエンド商品がしっかり設計されているかどうかです。
バックエンド商品は勇気を持って高く設定する
バックエンド商品とは、リピート客やファンになったお客さんに販売する、高価格・高利益の商品です。ここでは遠慮は不要。利益を最大化するための価格設定をするのが基本です。
ポイントは以下のとおり:
- 単価を高く:高額でも価値があれば売れる
- 薄利多売より厚利少売:小規模事業者は少数精鋭で利益を出す
- 本当に欲しい人だけに売る:無理な営業不要、価値が伝わる人に届けばOK
たとえば、オンライン講座やコンサル、会員制サービス、継続課金のコミュニティなどがバックエンド商品として有効です。
値付けは「アート」である
値付けに正解はありません。市場は常に変わり、消費者の価値観も日々変化します。一時は成功した価格でも、時間が経てば通用しないこともあります。
だからこそ、価格は“感覚”と“実験”が必要な世界。まさにアートです。
しかし、それでも守るべき「原則」はあります。
- フロントエンド商品は安く(信頼を得るため)
- バックエンド商品は高く(利益を得るため)
- 原価割れを恐れず、全体設計で収支を見よう
この鉄則を理解しておけば、価格戦略で大きく失敗するリスクを避けられます。
める配くん第4章:価格戦略でよくある失敗パターン
ここまで価格決定の基本と成功するための考え方を学んできましたが、最後の仕上げとして、ありがちな失敗例についても押さえておきましょう。
「こうすれば失敗する」という例を知っておくことで、逆に「こうすれば成功に近づく」という判断力が身につきます。
① フロントエンド商品を高くしすぎる
これは最も多い失敗のひとつです。
- 自分の商品に絶対の自信がある
- 安売りは価値を下げると思っている
- 手間がかかったから、それに見合う価格を設定したい
こうした考えから、いきなり高単価のサービスや商品を売ろうとする人がいます。
ですが、お客さんは最初からあなたを信用していません。
「この人の商品、本当に価値あるの?」という疑念を持っている状態で、いきなり高額商品を提示されても、買うわけがないのです。
結果、まったく売れない → 自信を失う → 値下げする → それでも売れない…という悪循環に陥ることに。
② フロントエンドとバックエンドの設計をしていない
よくあるのが「商品は1つだけ」というケース。
たとえば、
- 単発の講座しかない
- 単品の物販しかしていない
- 定期購入やアップセル、サービス継続の導線がない
これでは、いくら安価なフロントエンド商品で集客できても、継続的な収益化にはつながりません。
理想は
- フロントエンド商品で信頼を得る(例:1,000円のミニ講座)
- バックエンド商品で利益を出す(例:3万円の本講座)
この「収益の仕組み」がないと、価格をどう設定しても収支が合わなくなってしまいます。
③ 競合を無視して価格を決める
「自分はオリジナルだから」「価値があると思ってるから」といった理由で、競合商品とまったく異なる価格をつける人もいます。
ですが、これもかなり危険。
市場はお客さんが決める世界です。
- 似たようなサービスが5,000円で売られている
- 自分のサービスは8,000円
このとき、「どうして3,000円も高いのか?」が明確に伝わらなければ、ほとんどの人は買いません。
逆に、
- 他社:5,000円
- あなた:1,000円
と、安すぎると逆に「なんか怪しい」「価値が低そう」と思われてしまうリスクもあります。
重要なのは、市場価格をリサーチして、相場感のある価格に設定すること。そして、そこから「自分だけの価値(付加価値)」をどう加えるかを考えることです。
④ 時給換算で見ると全然割に合っていない
価格決めのとき、材料費やプラットフォーム手数料などは気にしても、自分の時間をコストとして計算していない人がとても多いです。
たとえば、
- ハンドメイド商品:1,000円で販売
- 材料費:300円
- 手数料:100円
- 製作時間:2時間
実際の利益は600円ですが、時給換算すると300円/時間です。これでは、ビジネスとして成り立ちません。
価格を設定するときは、必ず「自分の時間=労働コスト」も計算に入れること。
人気の習いごと特集第5章:初心者が取るべき実践的アクション
ここまで価格の決め方に関する基本、戦略、そしてありがちな失敗例を紹介してきました。では実際に、これから副業やフリーランスで稼ぎたい初心者は、どのように行動すればよいのでしょうか?
この章では、「実際に何から始めたらいいのか?」をステップ形式でお伝えします。
ステップ1:まずは市場リサーチをする
最初にやるべきは、自分が売ろうとしているジャンルの商品やサービスが、いくらで売られているかを調べることです。
- 似たジャンルのメルカリ商品
- BASEやSTORESでの価格帯
- ココナラやnoteなどのプラットフォーム
- SNSで話題になっている商品やサービス
ここで見るべきは「安い価格」ではなく、「人気があるものの価格」。つまり、実際に売れているもの、フォロワーやレビュー数が多いものを選びましょう。
ステップ2:自分の原価と時間を洗い出す
価格を決める前に、自分の商品・サービスにどれだけのコストがかかっているのかを、きちんと可視化しましょう。
例:ハンドメイド商品の場合
- 材料費:400円
- 梱包資材:100円
- 発送手数料:200円
- 製作時間:2時間(時給1,000円換算)
→ 合計原価:2,700円
この「自分の時間を含めた原価」をきちんと計算することで、最低限必要な販売価格の目安が見えてきます。
ステップ3:フロントエンドとバックエンドを設計する
ビジネスは単品勝負ではなく、導線(どうせん)=流れが大切です。
- フロントエンド:お試し版、ワンコイン体験、初月100円など、とにかく“試してもらう商品”
- バックエンド:継続サービス、講座、コンサル、高額商品など、“利益を取る商品”
たとえばこんな設計が可能です:
| 商品 | 内容 | 価格 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 初回お試し講座 | 30分Zoomで相談 | 500円 | 集客・信頼構築 |
| 通常講座 | 2時間の本格セミナー | 8,000円 | 利益商品 |
| 継続コンサル | 月1回×3ヶ月 | 30,000円 | 長期収益 |
こうした商品設計をあらかじめ考えておけば、フロントエンドでは無理に利益を出そうとしなくて済みます。
ステップ4:価格に「自分のストーリー」を乗せる
最後に大切なのが、「価格に自分の考えや背景を込める」ことです。
たとえば、あなたが設定した3,000円のオンライン講座。競合と比較して少し高めでも、
- 「この価格にした理由」
- 「この商品が生まれた背景」
- 「どんな価値があるのか」
を丁寧に伝えることで、ただの価格が「納得価格」になります。
価格に込めた想いを伝えることが、顧客との信頼をつくる第一歩です。
スモールビジネスを始めたい読者に直結するまとめ:価格はビジネスの生命線。まずは成功者のマネから始めよう
この記事では、「価格の決め方」について、ビジネス初心者でも実践できる考え方とステップを解説してきました。
改めて、重要なポイントを振り返ってみましょう。
● 価格決めの基本は2つだけ
- 原価+欲しい利益
- 原価割れは絶対NG。労力もコストとして考える。
- 人気商品と同じ価格にする
- 市場で成功している価格には、すでに「答え」が出ている。
● フロントエンドとバックエンドの役割を理解する
- フロントエンドは客寄せ用。赤字でもOK。信頼獲得が目的。
- バックエンドでしっかり利益を出す。高価格でOK。
このセット設計ができていないと、どんなに安く売っても利益は出ません。
● よくある失敗に注意!
- フロントエンドを高く設定して売れない
- 時給換算すると労力に見合わない
- 競合を無視した価格設定で失敗
- 価格を1つだけで完結させようとする
これらは、価格戦略を“単体”で考えているからこそ起こる失敗です。価格は「戦略」そのもの。全体設計で考えることがカギです。
● 初心者の鉄則:オリジナル戦略より、まずはマネ!
初心者のうちは、「オリジナルの価格戦略を組む」のは避けましょう。
- 価格で勝負する前に
- まずは市場を知る
- 成功者の価格と設計をマネする
ここからスタートするだけで、失敗の確率はグッと下がります。
● 最後に一言
価格設定とは、ビジネスの“根幹”です。
利益が出なければ、どんなに良い商品も、どんなに頑張っても続きません。情熱だけではご飯は食べられないからです。
まずは、
- 売れてる人の真似をしながら、
- 自分の原価と労力を計算し、
- 少しずつ“自分なりの価格戦略”を作っていきましょう。
稼ぐ力は、「価格決め」から育ちます。
今日の内容を、あなたのビジネスの現場でしっかり活かしていってください😊