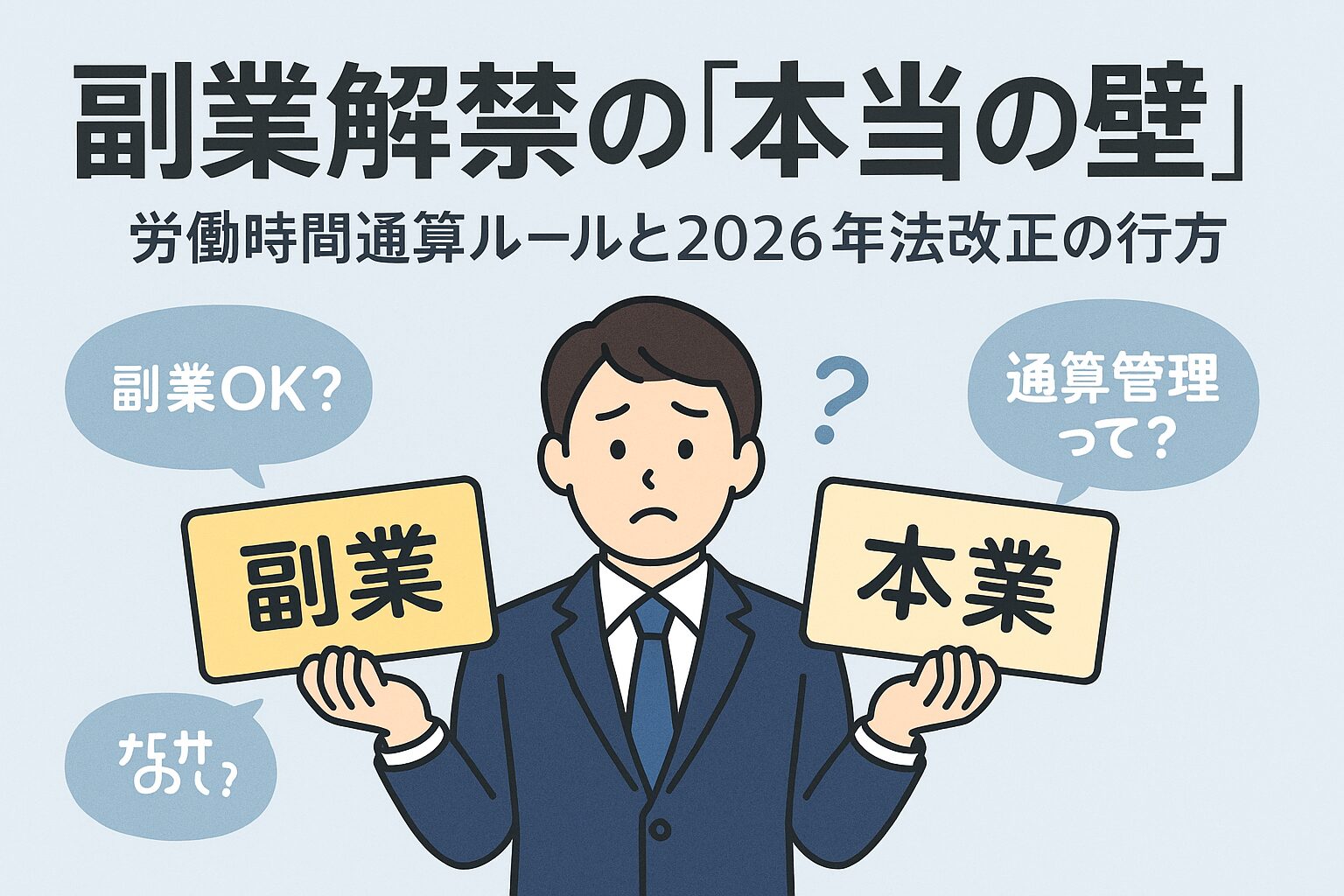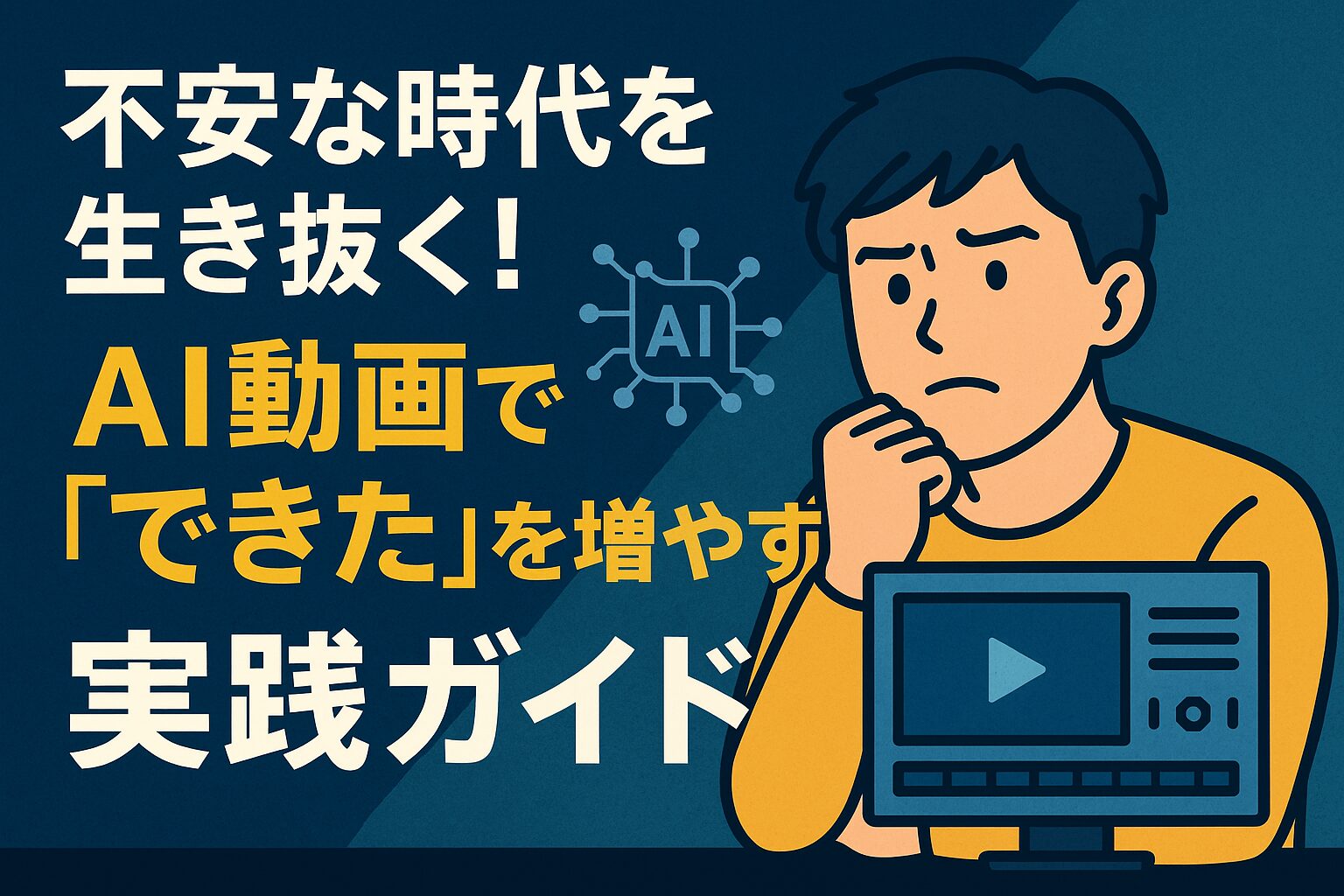第1章:はじめに
「副業、やってみたいけど、会社にバレたら面倒そう」「残業があるのに、他の仕事なんて無理だよ」——こんな声を耳にしたことはありませんか?
近年、「副業解禁」の動きが進む中で、働き手が一つの会社に依存せず、自分のスキルや興味を活かして複数の収入源を持つことが推奨されています。企業側も「多様な働き方を支援する」として副業・兼業の制度を整備するところが増えてきました。
ところが現実には、厚生労働省が2024年に行った調査で、副業・兼業を実際に行っている労働者の割合は、全体のわずか**3%**にとどまっていることが明らかになりました。政府が推進しているにも関わらず、なぜここまで低いのでしょうか?
その背景には、「労働時間の通算管理義務」という、企業にとって非常に重い法的・実務的負担があるのです。
この記事では、現行の労働法制度が副業・兼業にどのような影響を与えているのかを解説するとともに、今後予想される法改正の動きがどのようにこの状況を変えるのかについて詳しく掘り下げていきます。
これからの時代、複数の働き方を選べる環境づくりはますます重要になります。本記事を通して、「自分はどう働くか」「企業としてどう対応するか」を考えるヒントになれば幸いです。
マンツーマンの副業サポート【スキルコンシェルジュ】第2章:現状分析:副業・兼業が進まない理由
2-1. 副業・兼業解禁の波と実態のギャップ
政府は働き方改革の一環として、2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、企業に対して副業を容認する方針を示しました。企業もこの方針に沿って就業規則を見直す動きが進みましたが、それでも実際に副業・兼業をしている人は**わずか3%**に過ぎません。
この数値は、厚生労働省が2024年に実施した「副業・兼業に関する実態調査」によるものです。つまり、100人に3人しか実際に副業・兼業をしていないということになります。
2-2. 企業側の実施状況と対応のばらつき
調査によると、副業・兼業を「雇用型」で認めている企業は全体の**24.7%にとどまり、「フリーランス型」ではさらに少なく13.2%**でした。つまり、約7割以上の企業が副業に消極的または禁止している状況です。
これは以下のような企業の懸念によるものです
- 本業への影響:副業で疲弊し、パフォーマンスが落ちるのではないか
- 情報漏洩のリスク:競合他社での就業による企業秘密の流出
- トラブル時の責任問題:副業中の労災や健康問題への対応
2-3. 労働者側の事情と心理的ハードル
一方で、働く人側にも副業・兼業に対する不安があります。
- 「会社にバレたらどうなる?」
- 「就業規則違反にならないか?」
- 「本業に支障をきたしたら評価が下がるのでは?」
特に、労働時間の管理義務が本業と副業の両方に及ぶ現在の制度では、複雑なルールや申告義務により、心理的な負担が大きいのです。
このように、制度面・企業側・労働者側の三者にそれぞれの課題があることが、副業・兼業の実施率が伸びない理由となっています。
第3章:最大の障壁:「労働時間通算管理」とは?
副業・兼業が日本でなかなか浸透しない最大の理由として、「労働時間の通算管理義務」が挙げられます。これは、労働基準法第38条によって定められているルールであり、企業が副業・兼業を許可する上で最も大きな負担となっています。
3-1. 労働基準法第38条とは?
この条文では、以下のように定められています:
労働者が複数の事業所で働く場合、その全ての労働時間を通算して労働時間規制を適用する。
つまり、A社で1日6時間働き、B社で3時間働いた場合、合計で9時間となり、法定労働時間(1日8時間)を超えることになります。この1時間分に対して、B社が割増賃金(25%以上)を支払う必要があるのです。
3-2. 通算管理が企業に与える負担
この通算ルールがあることで、企業は副業先での勤務時間を把握しなければならなくなります。以下のような管理業務が必要になります
- 労働者からの副業スケジュールの提出
- 勤務時間の逐一集計と合算
- 法定労働時間を超えた場合の36協定(時間外労働協定)締結
- 超過分の割増賃金の支払い
- 違反時の労基署からの是正指導や指摘リスク
これらの実務対応は、中小企業にとっては非常に重く、「そこまでして副業を認める必要があるのか?」と考えてしまうのも無理はありません。
3-3. 労働者側の申告負担とジレンマ
通算管理の制度では、労働者自身にも副業先の労働時間を本業の企業に報告する義務が発生する場合があります。しかし、「副業がある」と明かすことで評価に影響が出るのではという不安や、「そもそも会社に知られたくない」という意識も根強くあります。
結果的に、
- 企業は管理できないから認めない
- 労働者は申告したくないから黙ってやる
- 結果的に制度の“裏”で副業を行う人が増える
という矛盾した状況が生まれているのです。
このように、労働時間通算の義務が副業制度の形骸化を招いているとも言えます。では、こうした障壁を取り除くために、国はどのような方針を取ろうとしているのでしょうか。
マンツーマンの副業サポート【スキルコンシェルジュ】第4章:法改正の動きと今後の方向性
前章で見た通り、現行制度の下では副業・兼業の推進が難しい構造的な問題があることが分かりました。こうした課題を受けて、政府は今、制度の見直しに本格的に乗り出そうとしています。
4-1. 規制改革会議の提言:通算義務の撤廃を提案
2024年、政府の規制改革推進会議は、労働基準法第38条にある労働時間の通算義務を見直すべきとの提言を公表しました。
この中で、「時間通算義務は欧米諸国には存在せず、柔軟な副業制度の導入が進んでいる」として、日本も同様に通算管理をやめる方向で法整備を進めるべきと指摘しました。
提言の背景には、「通算管理がある限り、企業も労働者も副業に積極的になれない」という根本的な問題意識があります。
4-2. 厚労省有識者会議の検討状況
この提言を受けて、厚生労働省は専門家や労使代表による有識者会議を立ち上げ、労働時間の通算ルールをどう改めるかについて議論を進めています。
現在検討されている方向性には、以下のような案があります:
- 通算管理の完全廃止
- 通算管理を義務ではなく「努力義務」にする
- 副業側の労働時間に関する「自己申告モデル」導入
これらの案は、年内にも結論が出される見通しで、これをもとに法改正案が取りまとめられる予定です。
4-3. 2026年に法案提出へ
政府関係者の発言によれば、2026年の通常国会を目処に、労働基準法改正案が提出される可能性が高いとされています。
もしこの法改正が実現すれば、企業にとっての管理負担は大幅に軽減され、副業・兼業がより現実的な選択肢として広がることが期待されます。
このように、副業・兼業を巡る法制度は大きな転換期を迎えようとしています。次の章では、実際にこの法改正によって私たちの働き方がどう変わるのか、具体的な影響について見ていきましょう。
【今すぐ無料で登録する】第5章:法改正で副業環境はどう変わる?
労働時間の通算管理義務が見直されることで、副業・兼業の環境はどのように変化するのでしょうか。ここでは、想定される変化やメリット、そして新たに登場する可能性のある「副業モデル」について解説します。
5-1. 通算管理の見直しがもたらすメリット
◉ 企業側のメリット
- 労働時間管理の負担が軽減:副業先の勤務時間まで把握する必要がなくなる
- リスク管理が容易に:36協定や割増賃金の扱いが簡素化される
- 副業禁止の根拠が弱まる:就業規則の見直しがしやすくなり、人材の多様化も期待できる
◉ 労働者側のメリット
- 心理的ハードルの低下:「会社に迷惑をかけるのでは」という不安が減少
- 選択肢の増加:副収入やキャリアの幅が広がる
- 自己成長の機会:本業とは異なるスキルや経験を積める場が拡大
5-2. 想定される「新しい副業モデル」
法改正が進めば、以下のような柔軟な副業の形が普及する可能性があります。
▷ 自己申告型モデル
- 労働者が副業先の労働時間を自己管理・自己申告するスタイル
- 本業の企業はその申告をもとに、健康管理や勤務調整を行うのみ
▷ 就業制限付き承認型
- 一定条件(週〇時間までなど)を設けて副業を許可
- 労働時間の通算管理は行わず、責任の所在を明確に
▷ 業務委託・ギグ型副業
- UBERやココナラのように、個人が自由に仕事を受託する形式
- 企業に雇用されない形態なら、労基法の通算義務の適用外となる
これらのモデルによって、企業と労働者の双方が実態に即した形で柔軟に副業を運用できるようになるでしょう。
5-3. 海外との比較:日本はどう変わるべきか?
欧米では、基本的に労働時間の通算制度は存在しないため、企業は自社の労働時間のみを管理すればよく、副業のハードルが低くなっています。
例えば:
- アメリカ:副業は個人の自由。企業は関与せず、法的責任も負わない
- ドイツ:健康への影響が出ない範囲で副業が可能。ただし、競業は禁止
日本もこれらのモデルを参考にしつつ、「過労防止」と「自由な働き方」のバランスを取った制度設計が求められています。
副業・兼業は、単なる「副収入」手段ではなく、自己成長やキャリア形成、生活防衛の一環でもあります。法改正によって、その可能性が一気に広がる局面が訪れようとしています。
次章では、こうした変化に備えて、企業と個人がどのような準備をしておくべきかについて考察します。
賢い人ははじめてる。ビジネスマンのための副業サービス【Saleshub(セールスハブ)】第6章:企業と働く人が備えておくべきこと
労働時間の通算管理が見直され、副業・兼業がより自由にできるようになると、企業も労働者も新しい働き方に対応するための準備が必要になります。この章では、双方が取るべき具体的なアクションについて解説します。
6-1. 企業側が検討すべきこと
◉ 就業規則の整備
副業・兼業を正式に認める場合、まず必要なのは就業規則の見直しです。以下のような項目を明記しておくとよいでしょう。
- 副業を許可する条件(職種・時間・目的など)
- 競業禁止の範囲
- 健康管理に関する申告義務
- 本業に支障がある場合の制限措置
◉ リスク管理のルール策定
- 情報漏洩対策:副業先に対する誓約書やガイドラインを作成
- 健康リスク管理:過重労働を防ぐための面談・申告制度
- 労災対応の明確化:副業中の事故・病気がどの労災に該当するか明示
◉ 人事制度との整合
- 副業を理由に評価を下げない仕組み
- 副業経験をキャリア評価に反映する制度
- 本業で得られないスキルを副業で補う「越境学習」の活用
6-2. 労働者が意識すべきこと
◉ 本業とのバランス管理
副業の自由度が高まっても、健康や生活を犠牲にしては本末転倒です。
- 本業に支障が出ないスケジュールを組む
- 睡眠や休息の確保を優先
- 短期・高負荷の副業はリスクが高いため要注意
◉ 副業先の選び方
- 信頼性のある企業やプラットフォームを選ぶ
- 報酬体系や業務内容が明確な案件に絞る
- 本業の情報やネットワークを持ち込まない
◉ 法律・税務の理解
- 所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要
- 社会保険や住民税への影響を把握しておく
- 雇用契約・業務委託契約の違いを理解しておくこと
法改正によって副業のハードルが下がることで、柔軟な働き方は今後ますます一般化していくでしょう。しかし、「自由には責任が伴う」という意識も必要です。
最後の章では、副業・兼業を取り巻く制度と働き方の未来について、全体をまとめていきます。
第7章:おわりに
副業・兼業をめぐる環境は、今まさに大きな転換点を迎えています。これまで日本の労働制度は、「1人1社でフルタイム勤務」を前提としてきましたが、個人の価値観やライフスタイルが多様化する中で、その前提が揺らぎ始めています。
今回見てきたように、現行の労働基準法による「労働時間の通算管理義務」は、副業・兼業の大きな足かせとなってきました。しかし、2024年の規制改革会議の提言と、それを受けた厚労省の有識者会議の動きにより、2026年には法改正が実現する可能性が高まっています。
この法改正によって、企業は過度な管理負担から解放され、労働者も副業に対する不安や心理的障壁を取り除くことができるようになります。そして、それは単に「収入を増やす」ための副業ではなく、「スキルを磨く」「人脈を広げる」「自分らしく働く」といった多様な目的を達成する手段としての副業の普及を意味します。
副業・兼業の拡大は、働き方に柔軟性をもたらすと同時に、企業にとっても人材の活用や育成に新たな可能性を開くものです。今後の制度改正を正しく理解し、自社の方針や個人の働き方にどう取り入れていくかを検討することが、変化に備える第一歩となるでしょう。
2025年の今、制度改革の進展を見据えて、企業も働く人も「今できる準備」を始めるタイミングです。副業・兼業を“選べる働き方”として前向きに捉え、新しい時代にふさわしい働き方を築いていきましょう。