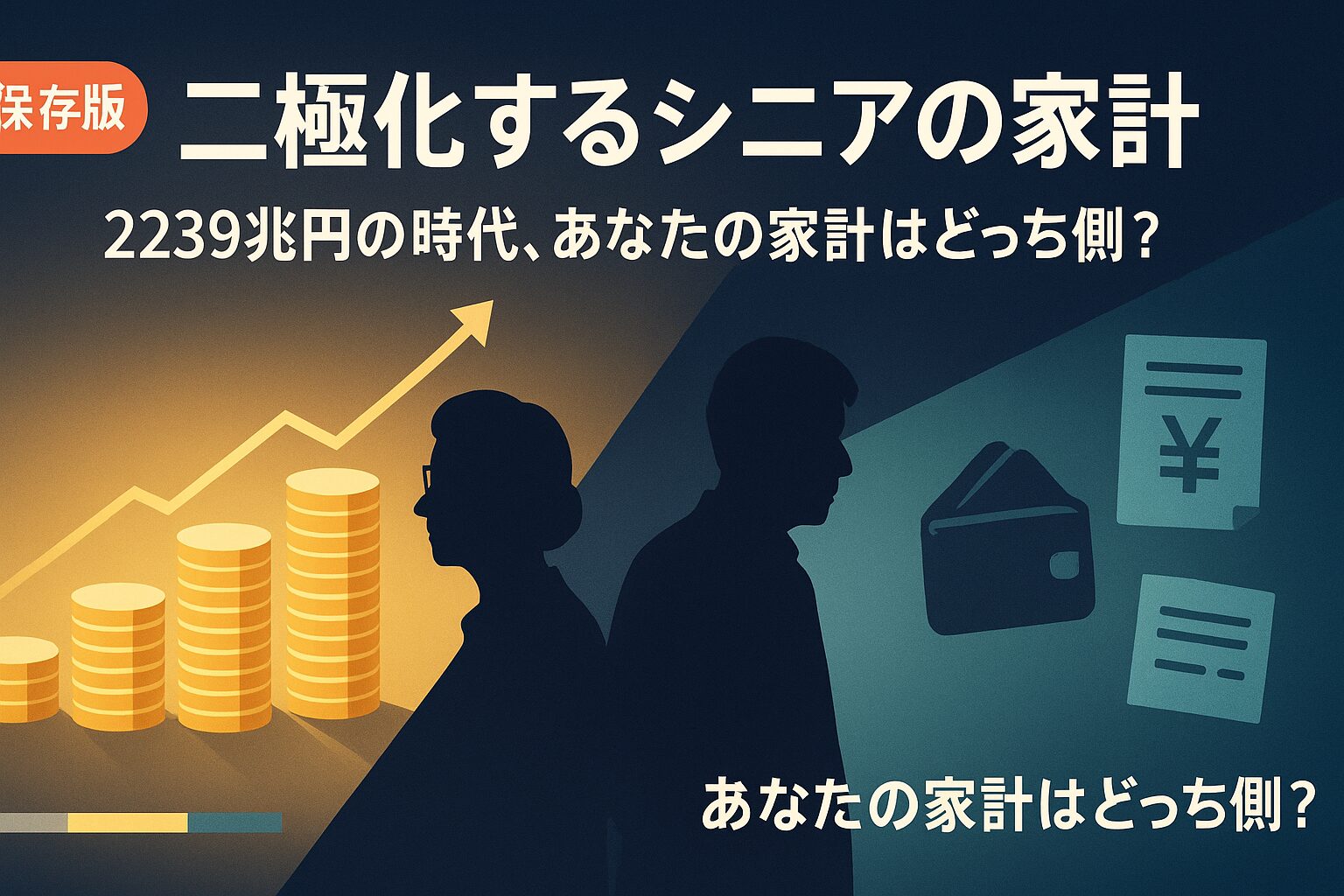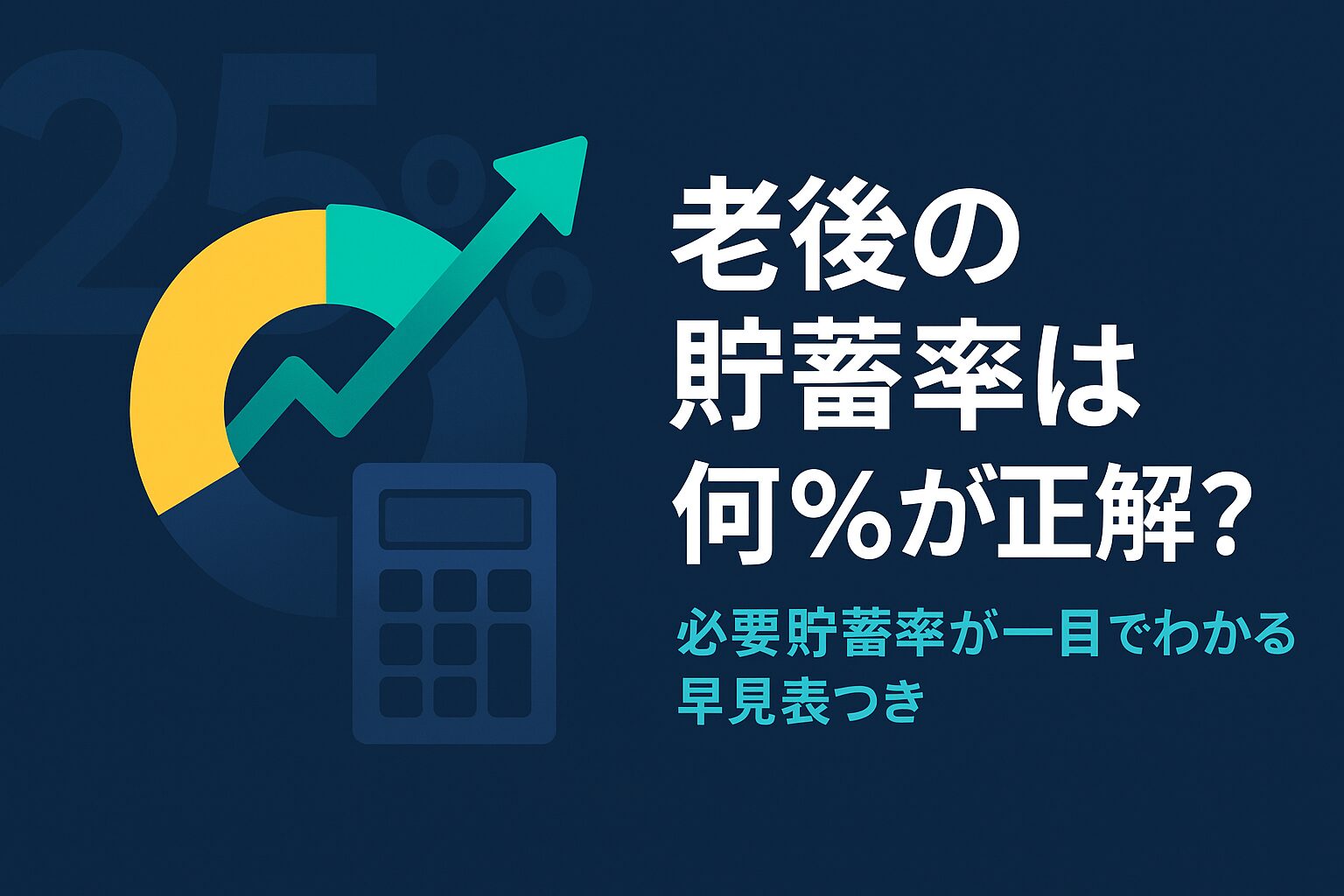家計全体のお金は記録的に増える一方、あなたの家計はどうでしょうか。日本銀行の資金循環統計では家計の金融資産が2239兆円と過去最高。しかし見出しの裏側では、高齢層で「非保有」と「3000万円以上」が同居する二極化が起きています。この記事は、その数字の正しい読み方と、今日から使える対策を、図表と具体例でまとめた保存版です。
参考にした主な一次情報
日本銀行 資金循環統計 2025年4–6月期速報、家計金融資産2239兆円。また構成比・四半期の増減については日銀の参考図表を参照。(家計金融資産が2239兆円、前年比+1.0%、前期末比+39兆円など)〔日銀ページへの総合入口〕。(日本オリンピック委員会)
朝日新聞ほか速報解説。家計金融資産が過去最大に、株高と新NISAが追い風。(朝日新聞)
J-FLEC 家計の金融行動に関する世論調査 2024年。単身・二人以上世帯の60代に関する非保有比率、平均・中央値の参照(J-FLECの集計を紹介する二次解説)。(All About(オールアバウト))
金融庁 新しいNISAの公式解説。年間投資枠、総枠1800万円、売却で簿価分が翌年以降に復活のルール。(金融庁)
厚生労働省 高額療養費制度の見直し資料(2025年8月以降に上限改定)。(厚生労働省)
厚生労働省リーフレットなど 高額介護サービス費の上限額(一般世帯の月額上限4万4400円ほか)。(厚生労働省)
新NISAを使うには証券口座が必要です。迷ったら手数料と使いやすさで選びましょう。主要ネット証券の最新キャンペーンはこちら。
新NISAに対応した証券口座を比較する1. いま何が起きているのか
2025年6月末の家計金融資産残高は2239兆円。四半期で39兆円増、前年比でも増勢を保ち、名実ともに過去最高です。背景は株価の上昇と新NISAの普及による投信・株式の増加。マクロの器は大きくなりました。(日本オリンピック委員会)
一方で、60代の資産分布に目を凝らすと「金融資産非保有」と「3000万円以上」が同時に厚い、はっきりした二極化が観察されます。単身60代では非保有が約3割、二人以上世帯でも約2割。平均と中央値の乖離も大きく、見出しの数字だけでは実態を誤読しやすい構図です。(All About(オールアバウト))
2. データで読む家計金融資産2239兆円
時点と水準
・時点 2025年6月末(2025年4–6月期 速報)
・残高 2239兆円、前年比+1.0%、前期末比+39兆円
・押上げ要因 株価上昇、新NISAを通じた投信・株式の買い増し など
出典 日本銀行 資金循環統計(速報)、朝日の速報解説。(日本オリンピック委員会)
資産の内訳イメージ
現金・預金が約5割、保険・年金が約4分の1、株式・投資信託などのリスク資産が残りという構図は大きく変わっていませんが、直近四半期は評価益の寄与で投信・株式の伸びが目立ちました。(日本オリンピック委員会)
テキストグラフ 家計金融資産の内訳(概算構成比のイメージ)
現金・預金 ██████████████████████████████ 約5割
保険・年金 ██████████████ 約1/4
株式等 ███████ 1割強
投資信託 ████ 数%台後半
その他 ██ 数%
出典:日銀 資金循環統計 2025年4–6月期速報(概算イメージ)。
四半期トピック
・4–6月期は例年ボーナス期の資金流入があり、加えて株価上昇の評価益が残高を押し上げました。(NLI Research Institute)
3. 60代の三割ゼロは本当か。調査定義と分布を読み解く
調査でいう金融資産とは
家計の金融行動に関する世論調査における金融資産は、運用や将来備えのために保有する預貯金・投信・株式・保険などを指し、日常の出し入れに備えた普通預金などの当座残高は含めません。したがって金融資産非保有は「生活口座も含めて完全に0円」を意味しません。ここが誤解ポイントです。(All About(オールアバウト))
分布の実数
・60代 単身世帯 金融資産非保有 27.7%、3000万円以上 16.8%、平均1679万円、中央値350万円
・60代 二人以上世帯 金融資産非保有 20.5%、3000万円以上 20.0%、平均2033万円、中央値650万円
出所はいずれもJ-FLEC 2024の集計を紹介する二次解説。(All About(オールアバウト))
テキストグラフ 60代の分布(上位・下位に厚み)
単身60代 非保有[███████████] 27.7% 3000万円以上[███████] 16.8%
二人以上 非保有[████████] 20.5% 3000万円以上[████████] 20.0%
平均と中央値の差:単身 1679万 vs 350万、二人以上 2033万 vs 650万
出典:J-FLEC 2024の要約記事より再構成。
読み取りのコツ
・非保有は生活口座を含まない定義。
・平均は富裕層に引っ張られやすく、実態把握は中央値重視。
・同じ60代の母集団内でゼロと3000万円以上が同時に厚い、これが二極化の実像です。
4. なぜ二極化が進むのか
収入と制度の経路差
就業履歴や厚生年金加入歴の厚みが老後キャッシュフローを分けます。平均的賃金・標準ケースの年金月額は夫婦でおおむね23万円前後という目安が示されますが、加入歴が薄いと年金のベースが下がり、貯蓄からの補填が増えます。(レゾナバンク)
住宅・教育費の持ち越し
住宅ローン残の長期化や子の進学ルート次第で、60代に入っても家計の固定費が重くなりがち。国公立で4年合計約240〜250万円、私立は文系で約400万円、理系で500万円以上という目安感は、家計の貯め期を押し下げます。(ジョヤバンク)
医療・介護の制度理解の差
高額療養費制度には年齢・所得ごとの月額上限があり、2025年8月からの上限見直しも予定されています。上限を把握していれば過度の予防的貯蓄を抑制しやすく、知らなければ現金比率を過大化しがち。(厚生労働省)
介護では高額介護サービス費があり、一般的な所得の世帯は月額上限4万4400円などの基準があります。(厚生労働省)
金融リテラシーと行動
全国3万人規模の金融リテラシー調査では、知識と行動の相関が示唆されます。長期・分散・低コストを理解し、制度を継続活用できるかが、資産価格の追い風を取り込めるかどうかの分水嶺になります。(知るぽると)
5. 今日からできる対策チェックリスト
まずは家計版BS/PLを一枚で
資産(現金・預金、新NISA、iDeCo、投信、株式、保険解約返戻金、外貨、ポイント等)と負債(住宅・教育・自動車ローン、カードリボ)を棚卸し。収入と支出のPLは固定費と変動費に分解。A4一枚で月末10分更新。
守りから攻めへ
1 緊急資金 生活費3〜6か月分を普通預金に確保
2 高コスト負債 カードリボ・分割は最優先で完済
3 制度の自動化 新NISAとiDeCoをセットで
新NISAのキモ
・年間投資枠はつみたて枠120万円、成長投資枠240万円、総枠1800万円
・売却すると翌年以降に簿価分だけ総枠が復活し再利用できる
・非課税期間は無期限、配当・分配・譲渡益も非課税
すべて金融庁の公式解説で確認できます。(金融庁)
iDeCoの基本
・拠出上限は職業区分で異なるため、まずは自分の区分と上限を確認
・受給開始は60〜75歳の間で選択可能
・節税と長期積立の自動化を両立させる
医療・介護の上限を家計ルールに埋め込む
・高額療養費制度の上限(年齢・所得区分別)と、2025年8月からの改定点を確認し、家計ノートに上限額をメモ。(厚生労働省)
・高額介護サービス費の月額上限を把握。一般的な所得世帯の上限4万4400円など。(厚生労働省)
テキスト表 チェックリスト
[ ] 家計版BS/PLをA4一枚で作成(更新日:毎月末)
[ ] 緊急資金:生活費 3〜6か月
[ ] 高コスト負債ゼロ化(カードリボ・分割)
[ ] 新NISA:つみたて枠→成長枠の順で自動積立
[ ] iDeCo:区分・上限を公式で確認し拠出開始
[ ] 医療・介護の上限制度を家計ノートに記入
[ ] 年1回の資産配分と手数料の棚卸し
6. ケーススタディ 二つの家計設計
ケースA 60代単身 金融資産非保有からの再スタート
前提 賃貸、年金手取り14万円、生活費13万円、生活口座60万円
目標 無理なく自動化し、5年で配当・分配を月1000〜3000円に
ステップ
1 固定費見直しで月1万円の余力を捻出、黒字1万円と合わせて月2万円を確保
2 18か月で緊急資金を60万→78万円(生活費6か月分)へ
3 以降は毎月2万円を、新NISAでつみたて1万円、成長枠1万円に自動化
4 高配当ETFの想定利回り3.5%なら、42万円の投資額で年1.47万円(約月1225円)の分配金が目安
落とし穴
一括投資は避ける、カードリボは即ゼロ化、制度の上限を把握し過度な現金偏重を避ける。
ケースB 60代夫婦 退職金あり 月5万円の上乗せ収入を狙う
前提 持ち家、ローン残200万円、退職金1500万円、預貯金1000万円、年金23万円、生活費25万円
目標 投資から平均月5万円(年60万円)を安定的に捻出
配分の考え方
・現金バケツ 24か月分 600万円
・安定バケツ 300万円(繰上げ・短中期債券等)
・成長バケツ 1600万円(新NISAと課税口座で段階投資)
新NISAを5年で満額に
年360万円×5年=総枠1800万円
・成長枠 240万円/年 高配当ETF中心(想定利回り3.5%)
・つみたて枠 120万円/年 全世界インデックス(分配1.5%想定)
5年後の非課税内キャッシュフロー試算 合計年約51万円(月4.25万円)。不足分は全世界から年1%弱の部分売却で9万円を補い、合計で年60万円。ルールは平時から紙に明文化。
年度別の育ち方イメージ
年度 新規投資額 年の終わりの非課税内キャッシュフロー累計
1 360万円 約10.2万円/年(高配当8.4 + 全世界1.8)
2 360万円 約20.4万円/年
3 360万円 約30.6万円/年
4 360万円 約40.8万円/年
5 360万円 約51.0万円/年
手順どおりに進めるなら、ここで口座を作って自動積立まで設定すると止まりません。自分で選ぶのが不安な方は自動運用型も選択肢です。
7. まとめ図解 一枚でわかる設計図
ASCII図 解決の順番とルール
[固定費見直し] → [緊急資金3〜6か月] → [新NISAつみたて自動化] → [成長枠で配当の種]
↓ ↓
[高コスト負債ゼロ化] [現金バケツ 1〜2年分]
↓
[定率取り崩し 2.5〜3.5%]
↓
[下落時は取り崩し停止+現金で代替]
制度の橋:高額療養費・高額介護サービス費の上限を家計ノートに明記
8. よくある質問
Q1 新NISAは売却すると枠が消えるのでは
A 翌年以降に売却商品の簿価分が総枠に復活します。年間投資枠と違い、総枠は簿価残高で管理されます。公式の図解が分かりやすいです。(金融庁)
Q2 医療費が高額になったときの備えはどれくらい必要か
A 月内の自己負担には年齢・所得ごとの上限があり、2025年8月に見直し予定です。まず自分の区分と上限額を確認しましょう。(厚生労働省)
Q3 介護費は青天井で増えるのでは
A 高額介護サービス費で月額上限があり、一般的な所得の世帯は4万4400円が基準です。詳細は自治体窓口や厚労省リーフレットで確認を。(厚生労働省)
Q4 平均と中央値のどちらを見るべきか
A 分布の偏りが大きいテーマでは中央値が実態に近いことが多いです。60代では非保有と3000万円以上が同時に厚く、平均だけでは実像が見えません。(All About(オールアバウト))
資産の見える化が進んだら、相続や書類の保管も一緒に整えましょう。家族が困らないシンプルな仕組みを先に。
相続と書類の整理をはじめる9. サイト内関連記事
終わりに
マクロの記録更新に安心しすぎる必要はありません。大事なのは、あなたの家計が不測の事態に耐え、目標に近づく仕組みを持っているかどうか。固定費の見直し、緊急資金、制度の自動化、現金バケツと定率取り崩し。やることは多く見えても、順番に組めば難しくありません。この記事をそのまま家計ノートに貼り、チェックを一つずつ埋めていきましょう。
注意事項
本記事は一般的な情報提供です。投資・税務・社会保障の最終判断は、各人の属性・家族構成・就労状況・保有資産・居住地で異なります。制度の最新情報は必ず公式ソースで確認してください。家計の重要な意思決定は、専門家による個別アドバイスもあわせて検討を。