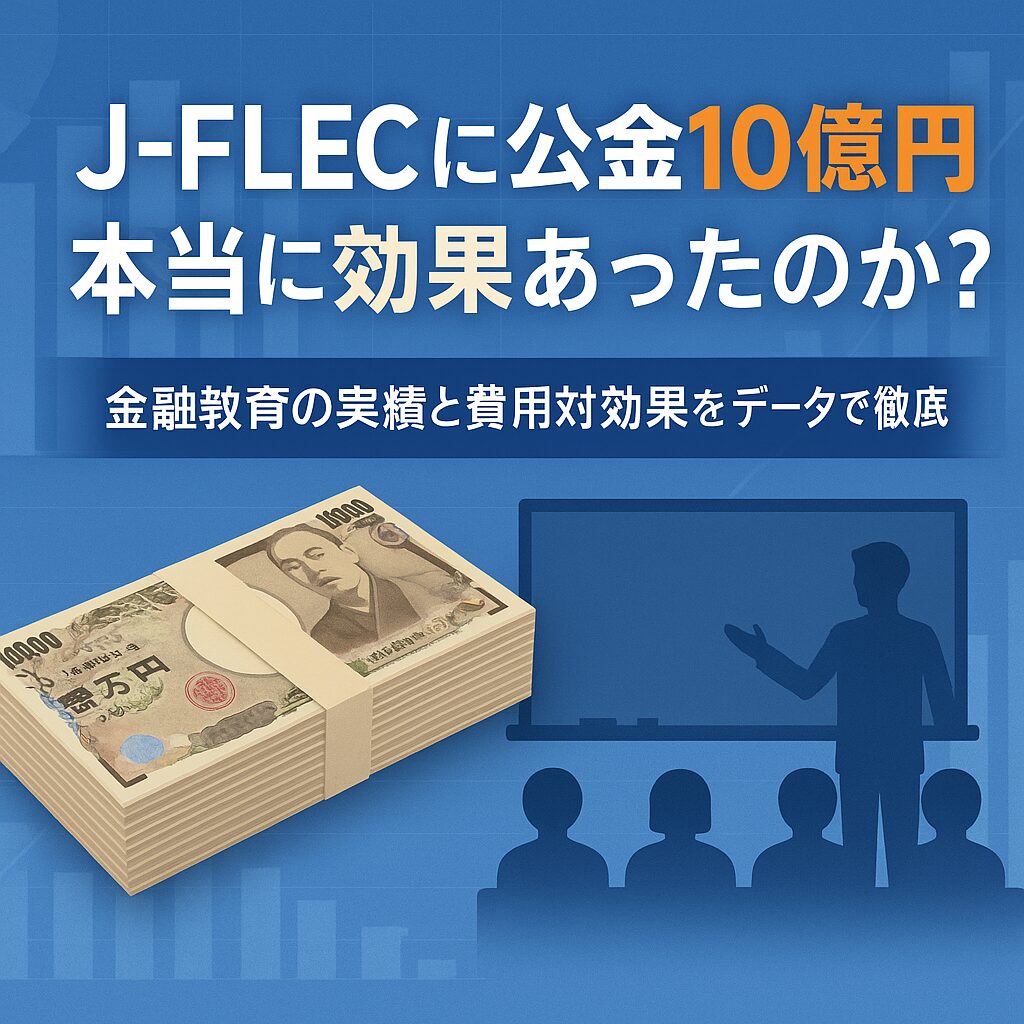この記事のゴール
- 「株高不況」の正体をデータで整理し、家計の購買力を守るための実践策(短期・中期・長期)を具体的に提示する。
はじめに
株価は上がっているのに、日々の買い物は高く感じる。貯金は増えているはずなのに、なぜか生活は楽にならない。そんな違和感の正体が、いわゆる株高不況だ。本稿では、家計の購買力が削られるメカニズムをやさしくほどき、今日から実行できる防衛策を、図表とテンプレ付きでまとめた。難しい専門用語は最小限。読み終わった瞬間から、家計の数字が変わる一手だけ持ち帰ってほしい。
- 何が起きているのか
株価は高く、物価も上がり、賃上げの手応えは人によって差が大きい。つまり、資産を持つ人ほど追い風、現金比率が高い人ほど向かい風になりやすい構図だ。
図1 現状のねじれ(直観図)
株価 ↑↑ 物価 ↑ 賃金 →/↓
\ | /
\ | /
家計の実感:苦しい(実質購買力が減る)
- なぜ購買力が下がるのか
要点は三つ。為替と輸入コストの上振れ、物価と賃金の時間差、そして現金偏重ポートフォリオだ。
図2 家計の購買力が減る仕組み
円安 → 輸入コスト上昇 → 企業の価格転嫁 → 物価上昇
↓
賃上げは年1回等で遅れ → 実質賃金低下
↓
預金金利 < 物価上昇率 → 現金の実質価値が目減り
豆知識
実質賃金=名目賃金から物価上昇分を引いた体感の稼ぐ力。名目が同じでも、物価が3%上がれば買える量は減る。
図3 実質のイメージ(概算)
インフレ率 3.0%
普通預金 0.2%
実質利回り ≒ -2.8%(3.0 − 0.2)
100万円の購買力は1年で約97.2万円相当へ
- 今日からできる家計防衛
まずは90日で効く手から。現金の置き場所を最適化し、固定費と住宅ローンを点検し、税優遇の準備を済ませる。
図4 現金の器マップ(置き場所の最適化)
| 用途 | 期間 | 置き場所の例 | 狙い | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 決済用生活費 | 1〜2か月 | メイン銀行の普通口座 | 利便性 | 残高は薄く保つ |
| 生活防衛資金 | 6〜12か月 | 普通預金の高金利口座+短期定期 | 少しでも利息を上乗せ | 流動性を確保 |
| 1年以上触らない余剰 | 1年以上 | 個人向け国債(変動10)や運用口座 | インフレ耐性または期待利回り | 元本保証と価格変動の違い |
固定費の即効ワザ
通信は実データ量で選ぶ。サブブランドやオンライン専用プランで、20〜30GBが月3千円前後の相場。データ消費が少なければ従量やトッピング型も有効。電気・ガスは請求明細で最新単価を確認し、比較サイトで郵便番号と使用量を入れて試算。省エネは待機電力オフ、給湯温度マイナス2℃、冷蔵庫の詰め込み過多を避けるだけでも効く。
住宅ローンの基本点検
変動なら金利が1%上がった場合の月返済を概算し、家計に先に織り込む。固定やミックスは、金利差×残高×残期間で一次判断し、詳細は金融機関のシミュレーターへ。繰上げ返済は生活防衛資金を削らない範囲で。
チェックリスト(今日やる3つ)
- 銀行アプリで金利を確認し、0.2%未満の普通預金は高金利口座へ移す
- スマホの直近3か月の使用量を見て、プランを1段階見直す
- 証券口座で世界株の自動積立を設定する
新NISAの第一歩:手数料に強い証券口座を先に用意する
つみたて設定まで最短10分。アプリで積立・残高をまとめて管理できます。
口座開設に進む(無料)投資には価格変動等のリスクがあります。内容を確認のうえご判断ください。
- 中期の投資設計と新NISA活用
税優遇の器をフル活用しつつ、通貨・資産の分散でインフレに負けない土台を作る。
新NISAのかんたん設計
年間360万円、生涯1,800万円の非課税保有限度額。つみたて枠(低コスト投信が中心)をコア、成長枠はサテライトで使う。売却すると取得価額ベースで翌年以降に枠が復活するが、その年の年間枠は増えない点に注意。
通貨分散の考え方
株式は世界株をコアにして自然に多通貨化。債券は為替ヘッジありを中心に、値動きのクッション役にする。ヘッジの有無は、株は原則なし、債券はありが実務で扱いやすい。
物価連動国債の位置づけ
JGBiは元本と利子が物価に連動する。物価上昇局面での土台づくりに向く。個人向け国債の変動10は金利に連動する別物で、元本保証と中途換金のしやすさが強み。
図5 モデル配分(たたき台)
| タイプ | 世界株 | 日本株・REIT | 外債ヘッジあり | 物価連動国債 | 現金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安定重視 | 40% | 10% | 30% | 20% | 0〜10% |
| バランス型 | 55% | 15% | 20% | 10% | 0〜10% |
| 成長重視 | 70% | 20% | 5% | 5% | 0〜10% |
運用ルール
目標配分から±5ポイント以上ズレたらリバランス。積立は止めない。株式が大きく下落したら、下落幅をトリガーに追加の積立を機械的に入れる。
| プラン | 月額目安 | データ量 | 申込 |
|---|---|---|---|
| DTI SIM | 3GB 990円 | 3GB/10GB | 公式で確認 |
| ロケットモバイル | 20GB 2,970円 | 20〜30GB | 公式で確認 |
| J:COM MOBILE | 基本0円+都度 | 都度購入 | 公式で確認 |
- 長期の収入強化ロードマップ
インフレ下で最も強いのは、稼ぐ力の底上げだ。狙い目はデジタルと業務をつなぐ領域。AIリテラシー、データ可視化、業務改善、クラウドやBIの初級資格から始め、社内の面倒な作業を自動化する小さな実績を作る。成果物を見える化し、年1回の給与交渉や転職面談に翻訳する。学習費用は公的な教育訓練給付の活用で自己負担を抑えられる。
図6 12か月の学習と行動
Q1–Q3 基礎:AI/データ入門修了、社内作業を1つ自動化
Q4–Q6 可視化:部署KPIダッシュボードを作成
Q7–Q9 証明:クラウド/BI等の初級資格に合格、社内LTで発表
Q10–Q12 交渉:職務経歴書を更新し、賃上げ交渉または面談
- 家計タイプ別モデルプラン
タイプA 独身・20代
目標は緊急資金6か月の達成と、少額でも自動で積み立てる仕組み化。配分の目安は株80、債20。通信やサブスクの削減分はそのまま積立へ。
タイプB 子育て世帯・住宅ローンあり
毎月の余剰を、緊急資金、NISA、教育資金、繰上げ返済原資に配分。変動金利なら金利が1%上がった場合の返済額を先に家計に組み込む。教育資金は5年以上先の分だけインデックスで分散。
タイプC 50代以降・退職前後
一気に現金化せず、3年かけて段階的に価格変動を下げるグライドパスを設定。取り崩しは課税口座→NISAの分配金→NISA元本の順で税コストを抑える。相続や受取人指定の整備も並行する。
- 為替と相場のもしもに備える
シナリオA 円安長期化
債券の為替ヘッジ比率を一時的に5〜10ポイント高め、偏りが出たら円資産に少し戻す。外貨影響の強い出費は時期をずらす。
シナリオB 円高反転
外貨資産の買い増しを3回に分けて予定し、債券のヘッジ比率を目標に戻す。必要があれば大型消費を前倒し。
シナリオC 株式の大きめ調整
積立は止めない。株式が目標から5ポイント以上下がればリバランス。下落幅が大きいほど追加の積立を段階的に入れる。生活防衛資金には手を付けない。
図7 行動カード(印刷推奨)
共通 積立は止めない/±5ptでリバランス/防衛資金6–12か月死守
円安 長期 債券ヘッジ+5〜10pt、外貨比率が高すぎれば一部円へ
円高 反転 外貨を分割買い、ヘッジ比率は目標に戻す
株安 -20%で積立1回追加、-30%でさらに1回
- よくある誤解Q&A
預金が一番安全か
名目は減らなくても、インフレ期は実質価値が減る。防衛資金と余剰で器を分けよう。
外貨だけ増やせば良いのか
偏らせないのが正解。株は世界株で自然分散、債券はヘッジあり中心。
新NISAは短期売買が得か
非課税は複利と時間で最大化される。基本は長期保有。
高配当だけで安心か
偏りのリスクと税コストがある。分散のコアを先に決めて、サテライトで少量に。
iDeCoとNISAの優先度
流動性を優先するならNISA、所得控除を重視するならiDeCo。両輪が理想。
- 12か月実行プランとまとめ
まずは家計の血流を良くする。現金の置き場所を整理し、固定費を削って、NISAの積立を自動化。投資は世界株をコアに、債券はヘッジあり、インフレ耐性として物価連動国債を少量。相場の変動は設計のテストと捉え、ルールと自動化で機械的に対応する。並行して、仕事での見える成果を積み上げ、年に一度の交渉や転職面談につなげる。これが、株高不況でも購買力を守り、少しずつ強くなる最短ルートだ。
図8 12か月の家計×投資×スキル実行表
月1 銀行口座集約と高金利口座へ移動、世界株の自動積立ON
月2 通信プラン見直し、差額を積立へ
月3 電気・ガスの比較と切替、待機電力・給湯温度見直し
月4 住宅ローン金利+1%耐性を家計に反映
月5–6 生活防衛資金を6か月分まで積み上げ
月7 債券ヘッジ比率と物価連動国債の比率を点検
月8 保険・サブスク棚卸し、浮いた固定費をNISAにスライド
月9 学習の中間点検、成果物を社内で披露
月10 副業または社内兼務の打診(規則と健康管理を確認)
月11 リバランス実施(±5pt基準)
月12 年間棚卸し(資産配分・家計KPI・年収)と来年の計画
最後に
今日の一手は、小さくてもいい。銀行アプリを開いて金利を確認し、世界株の自動積立を設定する。これだけで、見えない損を止め、未来の取り分を増やすスイッチが入る。家計は設計で変えられる。変化の速い時代だからこそ、ルールと自動化で、購買力を守り抜こう。