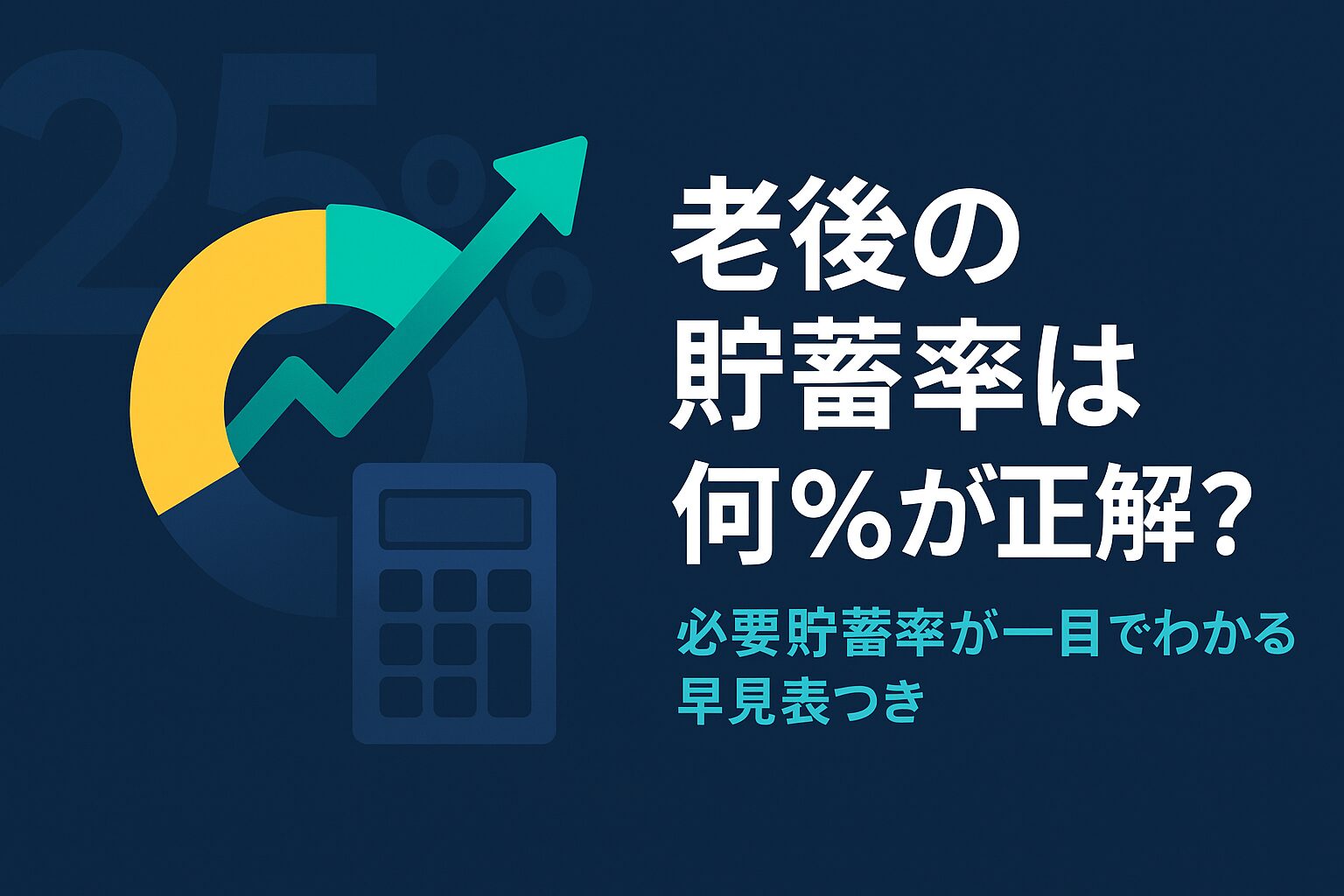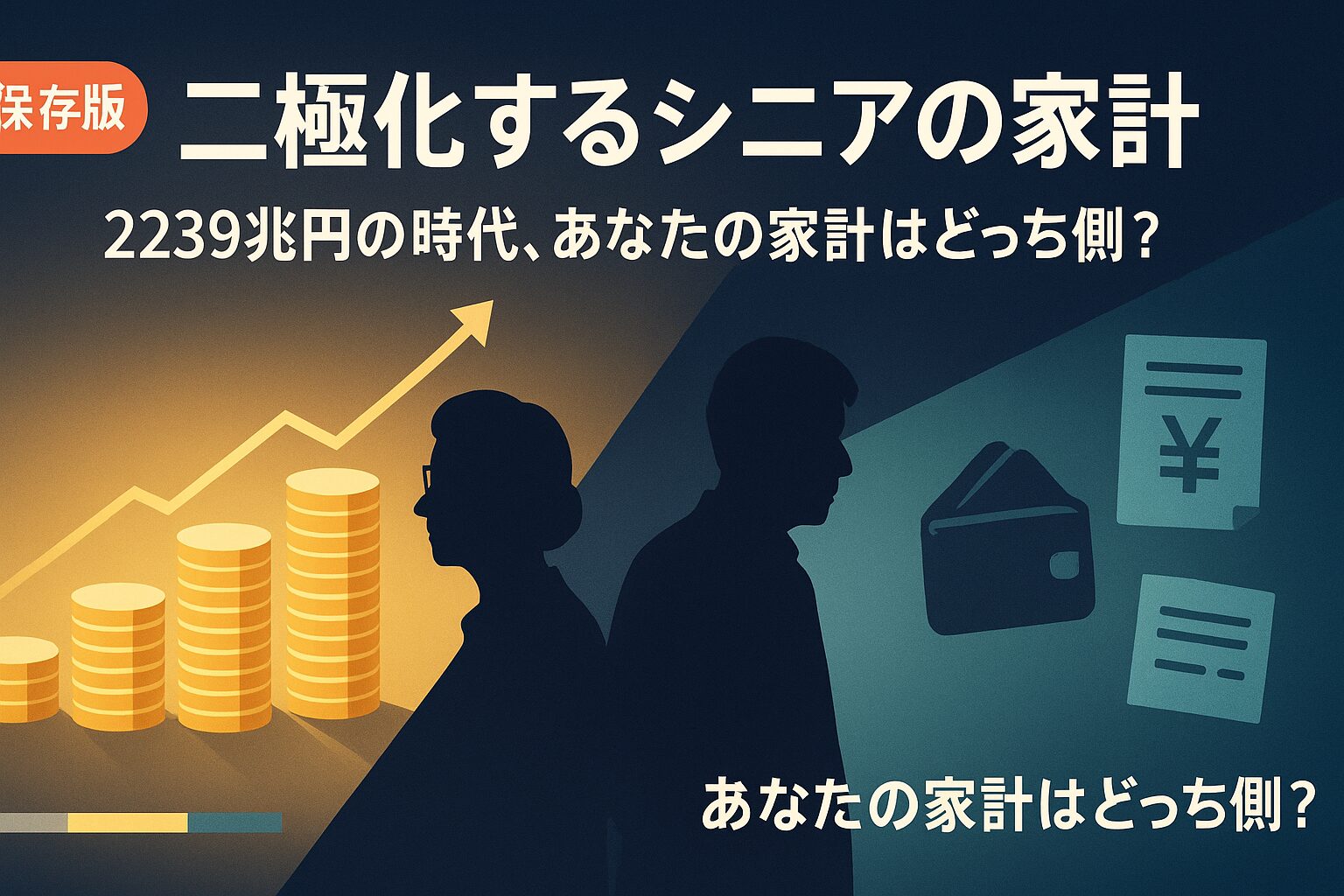1. はじめに
老後資金の悩みは突き詰めると「手取り年収に対して何%貯めればいいのか」に集約されます。答えは、老後の純支出、退職までの年数、想定実質リターン、現在資産の4つを入れれば一意に出ます。本記事は、計算の型、年率リターン別の早見表、新NISA/iDeCoの実務までワンストップで提供します。結論は、あなたの状況を式に入れればこの中に必ずあります。
2. 必要貯蓄率を決める前提をそろえる
前提は次の2つが最重要です。
・老後の年間純支出 S(老後の支出合計から年金などの確定収入を差し引いた額)
・退職までの年数 N
老後の支出は、現役時の支出から勤務由来で減る費用を引き、増える費用を足して見積もります。確定的な収入(公的年金、企業年金、個人年金、家賃、継続就労など)は差し引いて純支出にします。以降の計算は実質リターンで統一するため、Sは今の物価で置けば整合します。
表1 老後支出の調整チェック(例)
| 項目 | 現役時(万円/年) | 老後調整(±) | コメント |
|---|---|---|---|
| 生活費 | 200 | 0 | 水準維持 |
| 住居費 | 150 | −90 | ローン完済 −120、修繕 +30 |
| 通勤・外食 | 50 | −30 | 勤務由来減 |
| 医療・介護 | 20 | +20 | 予備費含む |
| 旅行・趣味 | 30 | +30 | 余暇増 |
| 保険 | 20 | −10 | 必要保障へ整理 |
| 合計 | 470 | −80 | 老後支出例 390 |
| 確定収入が年180万円なら、純支出 S=390−180=210万円/年といった具合です。 |
3. 25倍ルールで目標資産を決める
安全引き出し率(SWR)を4%と置くと、目標資産 M=S÷0.04=S×25(通称25倍ルール)になります。保守的に置くなら3〜3.5%、中庸は4%、攻めるなら4.5%など、家計のリスク許容度に合わせて選びます。
表2 SWRと必要倍率
| SWR | 必要倍率 |
|---|---|
| 3.0% | 33.3倍 |
| 3.5% | 28.6倍 |
| 4.0% | 25倍 |
| 4.5% | 22.2倍 |
| 5.0% | 20倍 |
4. 数式で一発計算:必要貯蓄率
ゴール M に対し、退職まで N 年で実質年率 r で積み立て、現在資産 A0 があるとき、年末拠出の年間積立額 PMT は次式で出ます。
A0(1+r)^N + PMT × {[(1+r)^N − 1]/r} = M
PMT = {M − A0(1+r)^N} ÷ {[(1+r)^N − 1]/r}
必要貯蓄率 s = PMT ÷ 手取り年収 Y
年初拠出(先取り)の場合は PMT をおおむね (1+r) で割れば近似可能です。名目で考える人は r=(1+名目利回り)/(1+インフレ率)−1 で実質に変換してから使います。
図1 計算の流れ(テキスト図)
[入力] S, SWR, r, N, A0, Y
→ M=S÷SWR
→ 係数F={(1+r)^N − 1}/r
→ PMT={M − A0(1+r)^N}/F
→ s=PMT/Y
→ 月額は PMT/12(先取りならさらに÷(1+r) 近似)
5. 年率リターン別の必要貯蓄率早見表
前提ベースケース
・純支出 S=120万円/年
・SWR=4% → M=3,000万円
・現在資産 A0=0、年末拠出、実質リターン r で計算
スケーリングは簡単で、あなたの S が違えば、表の金額に S/120 を掛ければほぼそのまま使えます。貯蓄率は s=PMT ÷ Y です。
表3 N=30年の年間PMTと月額
| r | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間PMT(万円/年) | 74.0 | 63.1 | 53.5 | 45.2 | 38.0 |
| 月額目安(万円/月) | 6.17 | 5.26 | 4.46 | 3.76 | 3.16 |
表4 N=20年
| r | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間PMT | 123.5 | 111.7 | 100.7 | 90.8 | 81.5 |
| 月額 | 10.29 | 9.31 | 8.39 | 7.56 | 6.79 |
表5 N=10年
| r | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間PMT | 274.1 | 261.8 | 249.8 | 238.7 | 227.6 |
| 月額 | 22.84 | 21.82 | 20.82 | 19.89 | 18.97 |
参考 N=25年
| r | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間PMT | 93.6 | 82.3 | 72.1 | 62.9 | 54.7 |
図2 既存資産があるときの効果(例 r=3%)
A0=100万円 → 年間PMTは
N=30で 約−5.1万円/年
N=20で 約−6.7万円/年
N=10で 約−11.7万円/年
退職までが短いほど、今の貯蓄の効きが大きいことが分かります。
6. 実質リターンの置き方と資産配分の目安
実質リターン r は希望ではなく配分とコストの帰結です。長期の経験則からの目安レンジは次の通り。
表6 資産クラスの実質リターン感
| 資産クラス | 実質rの目安 | 変動幅の感覚 |
|---|---|---|
| 世界株式 | 3〜5% | 年間で±15〜25% |
| 先進国債券 | 0〜2% | 年±3〜8% |
| 短期債・現金相当 | −1〜+1% | 小 |
| REIT | 2〜4% | 大 |
配分別の置き方例
20:70:10(保守) r=1.5〜2.0%
60:35:5(中庸) r=2.7〜3.5%
80:20:0(やや攻め) r=3.5〜4.3%
低コスト化は r をそのまま押し上げます。信託報酬を年0.3%から0.1%へ下げれば、期待実質rは+0.2%と等価です。
図3 r と必要PMTの関係(N=25、M=3,000、A0=0)
r=2.0% → 93.6万円/年
r=3.0% → 82.3万円/年
r=4.0% → 72.1万円/年
小さなrの差が毎年の積立に大きく効くことが見て取れます。
7. 目標に届かない時のレバー3つ
効果の大きい順に並べると、貯蓄率を上げる、実質rを底上げ、時間と支出を調整、の3本柱です。
表7 レバーの効き目(ベース M=3,000、r=3%、N=25、A0=0)
| 変更 | PMTへの影響 |
|---|---|
| r +0.5% | 約 −6% |
| N +1年 | 約 −5% |
| A0 +100万円 | 約 −5.7万円/年 |
| S −10% | PMTも −10% |
施策例
先取り自動積立、昇給・賞与の50%を自動で上乗せ、固定費5大見直し(通信・保険・住居・車・サブスク)、新NISA・iDeCo満額化、低コストインデックスへの集約、年1回のリバランス。やってはいけないのは、直近の流行テーマへの乗り換えでコストと分散を崩すこと。
baby planet(ベビープラネット)
妊娠・出産・教育費など、子育て期の保障と貯蓄を整えたい人に。申し込みの流れは公式ページのガイドを参照してください。
| サービス | こんな人に | 主な相談テーマ例 | 進め方の目安 | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|
| ガーデン | 初めての保険見直しを落ち着いて進めたい | 生命・医療の整理、家計とのバランス設計 | 公式ページで相談方法と手順を確認して予約 | 詳細を見る |
| ファインドイット | 比較しながら納得感を持って選びたい | 複数案の比較、家計最適化の方向づけ | 相談の流れを確認し、予約フォームから進行 | 詳細を見る |
| baby planet(ベビープラネット) | 妊娠・出産・子育て期の保障と貯蓄を整えたい | 学資準備、教育費、家族の保障 | 案内ページの手順どおりに申込→相談へ | 詳細を見る |
| パワープランニング | ライフプランを起点に保障を整えたい | 家計見直し、長期設計、リスクと保障の配分 | 公式の案内に沿って相談方法を選択 | 詳細を見る |
| リクルート | まず情報収集を広く行い、比較検討したい | 見直しの全体像、選び方の基礎を把握 | 公式ページで最新情報と進め方を確認 | 詳細を見る |
注記:費用、相談形態(オンライン・訪問の有無)や対象エリアなどの提供内容は変更される場合があります。申し込み前に必ず各公式ページで最新の条件をご確認ください。
8. 日本向け実務:新NISA・iDeCoの使い分け
新NISA(非課税無期限・年360万円・生涯1,800万円、成長枠はうち1,200万円)と、iDeCo(掛金全額所得控除+運用益非課税、受取時控除あり)は性格が異なります。流動性を重視するならNISA先行、節税額が大きくロックを許容できるならiDeCoを厚めに、が基本の指針です。公務員・DBありの人のiDeCo上限は近年引き上げられました。加入年齢など制度は今後も微修正があり得るため、口座開設時に公式最新情報も確認してください。
優先順位の型
流動性重視 → NISA先行
高い税率でロック許容 → iDeCo先行+NISA併用
自営業 → iDeCo最大活用→NISAへ
退職まで10年未満 → NISA厚め+iDeCoは控除メリットの範囲で
図4 税優遇で実質rを底上げ
iDeCo 年24万円の掛金 × 税率30% → 年7.2万円の確実な節税
NISA 利益への約20%課税がゼロ → 複利が強化され長期差が拡大
9. ケーススタディ3本
ケースA 20代独身 N=35、r=4%、A0=100万円、S=120万円、Y=420万円
(1+r)^N=1.04^35≒3.95、終価係数≒73.75
既存資産の将来価値 395万円
PMT=(3,000−395)/73.75=35.3万円/年(約2.94万円/月)
必要貯蓄率 s=35.3/420=8.4%
プラン例 月2万円+ボーナス 6万円/5万円=年35万円
ケースB 30代子育て N=25、r=3%、A0=500万円、S=150万円、Y=650万円
(1+r)^N≒2.0938、終価係数≒36.46
既存資産の将来価値 1,046.9万円
PMT=(3,750−1,046.9)/36.46=74.1万円/年(6.18万円/月)
必要貯蓄率 s=11.4%
プラン例 iDeCo2万円/月、NISA3万円/月、ボーナス7万円×2で年間74万円
ケースC 40代後半 N=15、r=5%、A0=1,500万円、S=180万円、Y=700万円
(1+r)^N≒2.079、終価係数≒21.58
既存資産の将来価値 3,118.5万円
PMT=(4,500−3,118.5)/21.58=64.0万円/年(5.33万円/月)
r=4%に保守化するとPMTは約89.8万円/年へ上昇。手数料圧縮、非課税、分散で確度の高い+0.3〜0.7%を積みに行く価値あり。
10. よくある質問(FAQ)
Q インフレが高い時の扱いは
A 実質リターンで統一。名目で考える時は r=(1+名目)/(1+インフレ)−1 で変換。rを保守に置く、Sを+5〜10%で感度チェックも有効。
Q 4%ルールは日本でも使えるか
A 目安の起点。分散と低コストが前提なら3.5〜4.0%が中庸、保守は3.0〜3.5%。取り崩し初期は調整可能なガードレール方式が実務的。
Q 途中で目標が変わったら
A 年1回の家計決算で S・N・r・SWR と A0 を更新し、式を回せば新しいPMTと貯蓄率が出ます。
Q 退職後も働く場合
A S から想定収入を差し引いて再計算。必要なら年金前と年金後の2期間モデルを使う。
Q 相場が暴落したら積立は止めるべきか
A 原則継続。生活費バッファと債券・現金クッションを持ち、厳しい年は積立額を一時的に縮める選択はあり。
11. まとめ(3行サマリーと実行チェックリスト)
3行サマリー
- 目標資産 M=S÷SWR(4%なら25倍)。
- 必要貯蓄率 s=PMT÷Y、PMTは式か早見表で即算出。
- 届かない時は、貯蓄率を上げる、実質rを底上げ、時間と支出を調整。
実行チェックリスト
・S・N・A0・Y をメモに固定
・SWRとrを決める(中庸はSWF4%、r3%が起点)
・M→PMT→sを算出
・iDeCoと新NISAの積立合計=PMTになるよう自動化
・信託報酬を0.1〜0.2%台に統一
・年1回のリバランスと再計算をカレンダー登録
12. 付録:計算テンプレ(コピペ可)
Excel/Sheets 年次版(年末拠出・後払い)
=LET(
S, 1200000, /* 純支出(円/年) */
SWR, 0.04, /* 安全引き出し率 */
r, 0.03, /* 実質年率 */
N, 25, /* 退職まで年数 */
A0, 0, /* 現在資産(円) */
Y, 6000000, /* 手取り年収(円) */
M, S/SWR,
FACTOR, ((1+r)^N - 1)/r,
PMT_year, (M - A0*(1+r)^N)/FACTOR,
s, PMT_year / Y,
PMT_month, PMT_year / 12,
VSTACK(
{"目標資産M(円)","年間PMT(円)","月額PMT(円)","貯蓄率s"},
{M, PMT_year, PMT_month, s}
)
)
月次厳密版(先取り/後払い両対応)
=LET(
S,1200000,SWR,0.04,r,0.03,N,25,A0,0,Y,6000000,
M,S/SWR,
rm,(1+r)^(1/12)-1, Nm,12*N,
FACTORm, ((1+rm)^Nm - 1)/rm,
PMT_m_end, (M - A0*(1+rm)^Nm)/FACTORm,
PMT_m_begin, PMT_m_end/(1+rm),
s_end, (12*PMT_m_end)/Y, s_begin, (12*PMT_m_begin)/Y,
VSTACK(
{"月末拠出(月)","月初拠出(月)","年換算貯蓄率(末)","年換算貯蓄率(初)"},
{PMT_m_end, PMT_m_begin, s_end, s_begin}
)
)
2期間モデルの計算枠
=LET(
S1,1800000, K,5, S2,1200000, SWR,0.04, r,0.03, N,25, A0,0, Y,6000000,
PV_bridge, S1 * (1 - (1+r)^(-K)) / r,
PV_perma, S2 / SWR,
M, PV_bridge + PV_perma,
FACTOR, ((1+r)^N - 1)/r,
PMT_year, (M - A0*(1+r)^N)/FACTOR,
s, PMT_year / Y,
VSTACK({"M合計","ブリッジ","永続","年間PMT","貯蓄率"},
{M, PV_bridge, PV_perma, PMT_year, s})
)
名目→実質の変換スニペット
=LET(r_nom,0.05, pi,0.02, r_real, (1+r_nom)/(1+pi)-1, r_real)
13. まとめ図解(ワンページで全体像)
図5 老後の必要貯蓄率を決める全体フロー(テキスト図)
┌───────────────────────────────┐
│ 1 入力するだけ │
│ S 老後の純支出(年) │
│ N 退職までの年数 │
│ SWR 安全引き出し率(3.5〜4%が起点) │
│ r 実質年率(配分とコストから決める) │
│ A0 現在資産、Y 手取り年収 │
├───────────────────────────────┤
│ 2 目標資産 │
│ M = S ÷ SWR │
├───────────────────────────────┤
│ 3 積立額の逆算 │
│ PMT = {M − A0(1+r)^N} ÷ {[(1+r)^N − 1]/r} │
│ s = PMT ÷ Y │
├───────────────────────────────┤
│ 4 改善のレバー │
│ r +0.5% ≒ PMT −6% │
│ N +1年 ≒ PMT −5% │
│ S −X% → PMTも −X% │
│ A0 +100万円 → PMT 約 −5〜12万円/年 │
├───────────────────────────────┤
│ 5 実務 │
│ 新NISA・iDeCoで税を味方に │
│ 低コスト指数×全世界株+先進国債券 │
│ 年1回リバランスと再計算 │
└───────────────────────────────┘
14. 関連記事への自動内部リンク(設置用リスト)
以下はWordPressでそのまま貼れる内部リンク案です。スラッグは例なので、自サイトのURLに置き換えてください。記事下や本文中に自動挿入して回遊性を上げます。
・関連記事: 新NISAの使い方完全ガイド(つみたて枠と成長枠の優先順位) [/nisa-how-to/]
・関連記事: iDeCoの受け取り戦略と税制の基本 [/ideco-tax-and-withdrawal/]
・関連記事: 4%ルールは日本で使えるか(安全引き出し率の考え方) [/swr-4percent-japan/]
・関連記事: 全世界株と先進国債券の組み合わせ(低コスト分散の作り方) [/global-stock-bond-allocation/]
・関連記事: 家計の固定費を年20万円削る方法(通信・保険・住居・車・サブスク) [/cut-fixed-costs-200k/]
・関連記事: リタイア前後のシーケンスリスク対策(取り崩しのガードレール) [/sequence-risk-guardrails/]
・テンプレ配布: 必要貯蓄率シート(Excel/Sheets) [/saving-rate-template/]
補足と注意
・本記事は実質リターンで統一しています。名目で管理したい場合は名目→実質変換の式を用いてください。
・制度や税制は今後変更される可能性があります。口座開設や拠出設定時は最新情報を確認のうえ判断してください。
・投資判断は自己責任です。不明点があれば金融機関や専門家に相談することをおすすめします。