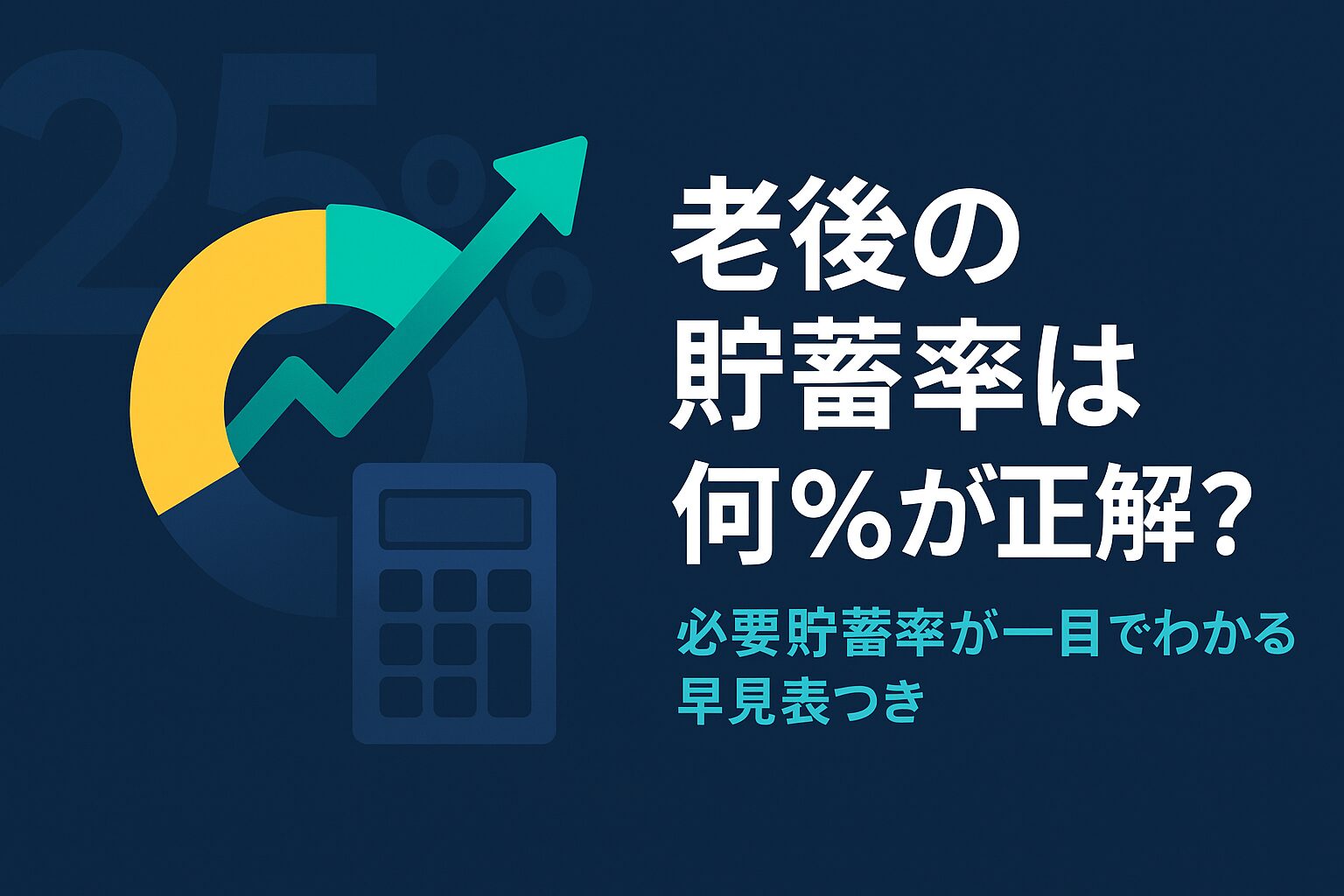冒頭の要点
・未成年にもつみたて投資枠を開放する方向で要望が提出された
・売却で空いた生涯非課税枠を当年中に再利用できる「当年復活」を要望
・つみたて枠など対象商品の拡充、口座開設後10年ごとの所在地確認の簡素化も掲げられた
・年末の与党税調→法案化→成立で最終仕様が確定する流れ
出典の一次情報は金融庁の税制改正要望PDFとNISA公式サイト、有識者会議の中間とりまとめ、主要メディアの報道です。
1. まず結論:今回の要望で何が変わる可能性?
金融庁は2025年8月29日に2026年度税制改正要望を公表。NISAをあらゆる世代で使いやすくする観点から、次の4本柱を示しました。
・未成年のつみたて投資枠の対象年齢見直し(こども家庭庁と共同要望)
・対象商品の拡充
・非課税保有限度額の当年中の復活
・NISA口座開設10年後等の所在地確認の手続き簡素化
いずれも要望段階であり、年末の与党税調で方向性が固まり、法案化・成立で最終仕様が決まります。
口座開設と同時にNISA設定まで最短で完了。積立は後から金額変更可。最短当日で仮審査。
広告リンク。最新の取扱や条件はSBI証券の公式サイトでご確認ください。
2. いまのNISAをクイック復習(数表つき)
制度の土台を30秒でおさらい。
図表1:2024年以降のNISAの骨格(簿価=取得金額ベース)
枠の種類 年間投資上限 生涯非課税保有限度額 対象商品の大枠 期間
つみたて投資枠 120万円 つみたて+成長の合計で 長期・積立・分散向け 無期限
成長投資枠 240万円 最大1,800万円(うち 上場株・ETF・REIT・ 無期限
合計 360万円 成長枠は最大1,200万円) 公募株式投信 等
重要ルール 売却すると簿価分の生涯枠が翌年以降に復活(年内には戻らない/現行)
制度の数字と復活ルールの詳細は金融庁のNISA特設サイトと公式スライドで確認できます。
ポイント
・年間投資枠は最大360万円(つみたて120+成長240)
・生涯非課税保有限度額は最大1,800万円(簿価ベース。成長枠は最大1,200万円)
・売却で空いた生涯枠は翌年以降に復活(現行)。当年復活は今回の要望事項
3. 変更点1:未成年もつみたて投資枠へ(こども支援)
要望の目玉の一つが、18歳未満にもつみたて投資枠を開放する方向性。家族単位で早期から長期・分散投資の習慣をつくる狙いです。報道でも同趣旨が伝えられました。
実務イメージ(制度化された場合)
・名義は子本人、手続運用は親権者が代理
・商品は現行のつみたて要件を満たす低コスト分散型投信が中心
・資金移転は贈与税の基礎控除110万円の範囲や名義預金リスクに留意(税務は別記事で詳説)
教育資金づくりの威力
・月1万円を年率4%、18年積み立てると約315.6万円
・月3万円なら約946.8万円
計算式:毎月積立の将来価値 = 毎月積立額 × { (1+年率/12)^(年数×12) − 1 } ÷ (年率/12)
試算根拠は単純複利。手数料・税等は考慮外。将来の成果を保証しません。
参考:月2万円・18年は年3%で約571.9万円、年5%で約698.4万円
挿入グラフ:教育資金の積立イメージ(18年、月額別、年率4%)
金額(万円)
1000 | █
900 | ███
800 | ████
700 | █ █████
600 | █ ██████
500 | █ █ ███████
400 | █ ██ ████████
300 | █ █ ███ █████████
200 | █ ███ ████ ██████████
100 | █ █ ████ █████ ███████████
0 +------------------------------------------------
月1万円 月2万円 月3万円
約315.6万 約631.2万 約946.8万
4. 変更点2:対象商品の拡充でリスク調整がしやすく
要望は、長期・安定的な資産形成を支援するため、NISAの一層の充実とともに対象商品の拡充を掲げています。具体的な品目名は示していませんが、有識者会議の中間とりまとめでは、つみたて枠の対象商品に関する考え方と今後の検討課題が整理されています。低リスク資産の選択肢が厚くなると、取り崩し期の設計もしやすくなります。
現行の大枠
・つみたて枠は長期・積立・分散に適した投信等(毎月分配型などは除外)
・成長枠は上場株・ETF・REIT・投信など幅広いが一定の除外あり
制度骨格は維持しつつ、選択肢の厚みを出す方向が読み取れます。
5. 変更点3:当年復活で年内の入替が現実に
現行は、売却で空いた生涯非課税枠が翌年以降に復活する仕組み。要望はこれを同じ年のうちに復活させ、年内の入替・買い直しを可能にするというものです。年間投資枠360万円が増えるわけではありません。
図解:当年復活のカラクリ(簿価ベース)
現行(当年は復活しない)
年初 空き生涯枠100 → 7月に簿価200を売却 → 当年の空きは100のまま → 追加買付×
翌年 空き生涯枠が+200 → 翌年に買い直し〇
要望後(当年に復活)
年初 空き生涯枠100 → 7月に簿価200を売却 → 当年の空きが+200 → 年内の買い直し〇
但し 年間投資枠360の上限は据え置き(上乗せされない)
金融庁スライドは「再利用できる非課税保有限度額が年間投資枠に上乗せされるわけではない」と明記しています。
数値で実感
・年内にすでに360万円を使い切っている場合、当年復活してもその年の追加買付は不可
・途中で簿価200万円を売って半年後に買い直すと、年率4%相当の上昇なら概ね2.02%分の機会を逃さずに済む計算(約4.0万円差)。短期の値動きは上下するため、あくまで参考値
6. 運用の地味だけど効く改善:所在地確認の簡素化
現行では、NISA口座の開設後10年(以後5年ごと)に金融機関が顧客の氏名・住所を確認し、確認ができないと新規買付が停止します。要望は、この手続を簡素化し、郵送中心の負担を減らす代替策の検討を求める内容です。
実務の現状は、証券会社のFAQや案内にも反映されています。つみたて枠の10年確認が未了だと新たな買付をNISAに受け入れられない取り扱いが明記されています。
図表2:所在地確認のライフサイクル
口座開設 ───────── 10年後 ───── 15年後 ───── 20年後 ……
↓確認 ↓確認 ↓確認
確認できない場合:新規買付が一時停止(現行) → 手続後に再開
いますぐできる予防策
・証券会社のマイページで住所・メール・電話を最新化
・口座開設日から10年後+以後5年のリマインドをカレンダー登録
・電子交付やアプリ通知をオンにして見落としを防ぐ
7. 家計インパクト:家族でどう設計する?試算とテンプレ
設計テンプレ1:0歳からの教育資金(未成年つみたてが実装された場合)
・0〜10歳は株式インデックス中心、11〜15歳はバランス型を増やし、16〜18歳は債券・短期資産へ段階シフト
・取り崩しは進学時期の1〜2年前から現金化を始める
設計テンプレ2:親+子の世帯合算
・親は現行NISAの年間360万円を10年、年4%で約4,322万円
・子は年72万円を10年、年4%で約864万円
・合計約5,186万円のイメージ(複利の概算、将来を保証しません)
設計テンプレ3:退職前後の守り
・退職5年前から株式70→60→50%、債券・現金を増やす段階シフト
・年3〜4%ルールなど、取り崩しの上限を決めて生活費と市場の波を切り離す
図表3:家族アロケーションの型
親口座(年360) 子口座(年120想定) 世帯合算
株式 60〜70 株式 80〜90 株式 総合65前後
債券 30〜40 債券 10〜20 債券 総合30前後
現金 1年分生活費 現金 少額 現金 必要月数に応じ調整
8. タイムラインとチェックポイント
想定スケジュール
・2025年8月29日 税制改正要望・有識者会議の中間とりまとめ公表
・2025年12月中旬 与党税制改正大綱
・2026年1〜2月 税制改正法案提出
・2026年3月ごろ 成立、附則で施行日が確定(項目により1月1日/4月1日など)
大綱では方向性、法案・附則で開始日や細目が明確になります。
チェックポイント
・未成年つみたての年齢範囲・口座管理の細部
・当年復活の具体的な計算・口座間の取扱
・対象商品拡充の具体項目
・所在地確認の代替策(オンライン同意、eKYC等が示されるか)
図表4:情報収集の動線
年末:大綱 → 金融庁サイトの解説・Q&A更新 → 各社のFAQ
年始:法案・附則 → 実施時期と手続 → 積立設定・入替の順番を調整
9. よくある誤解Q&A
Q. 当年復活が実現したら、その年に360万円以上買えるのか
A. 買えません。年間投資枠360万円は据え置きで、上乗せにはなりません。
Q. 売値ベースで枠が戻るのか
A. 戻るのは簿価(取得金額)ベースです。評価益・評価損は枠の大小に影響しません。
Q. 未成年つみたてはいつから始まるのか
A. いまは要望段階。大綱→法案→成立で開始時期が確定します。
Q. 2023年までの旧NISA・ジュニアNISAはどうなる
A. 旧制度の非課税期間のまま保有でき、2024年からの生涯非課税枠とは分けて管理されます。ロールオーバーは不可。
Q. 所在地確認はもう不要になるのか
A. まだ「簡素化の要望」の段階。現行では10年毎(以後5年毎)に確認が必要で、未了だと新規買付が停止します。
10. まとめ図解:全世代型NISAの全体像
図解はテキストでそのまま貼れるように設計しています。社内資料や解説スライドにも流用可。
図5:全世代型NISAの狙いと施策の対応関係
課題(世代別) 施策(要望) 実務メリット
未成年:早期に慣れたい つみたて投資枠の対象年齢見直し 教育資金づくり/複利期間の最大化
現役:入替したい 非課税枠の当年中の復活 年内にコスト低い商品へ乗り換え可
高齢:価格変動を抑えたい 対象商品の拡充 取り崩し設計の自由度アップ
全員:手続が面倒 所在地確認の簡素化 積立停止リスクの低減・負担軽減
図6:年内の入替シナリオ(当年復活を使う)
1 月〜3 月 既存ファンドを積立
7 月 コスト高ファンドを部分売却(簿価200万)
7 月〜12 月 空いた生涯枠が当年に復活 → 年内の残り年間枠の範囲で低コストへ買い直し
注意 年間360万円の上限は超えられない
図7:家族の役割分担テンプレ
親:成長投資枠でETFや個別株も活用(60:40へ徐々に)
子:つみたて枠で全世界株式・バランス中心(未成年解禁が前提)
世帯:生活費の現金バケツ(6〜12か月)を別管理
いまNISAを始めるならここから
口座開設と同時にNISA設定まで最短で完了。積立は後から金額変更可。最短当日で仮審査(各社の審査状況により異なる場合があります)。
広告:A8.net提携案件
| サービス名 | 種別 | NISA対応 | 強み | こんな人に | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
|
松井証券
|
総合ネット証券 | つみたて投資枠・成長投資枠に対応 | 取扱商品が広い。ランキングや情報ツールが充実。NISAの導線がわかりやすい | 初めてのNISAを幅広く活用したい人 | 公式サイトへ |
|
ひふみ投信
|
直販投信(運用会社の直接販売) | 直販で新NISA口座の開設手続きに対応(ひふみシリーズの購入に限る) | ひふみシリーズを長期で積立。直販ならではの情報提供やイベント | 特定ファンドをNISAでコツコツ積立したい人 | 公式サイトへ |
|
サクソバンク証券
|
外国株・CFD等に強いネット証券 | NISAは非対応(課税口座のみ) | 海外株の取扱市場が広い。低コスト施策やツールが豊富 | NISA外で海外株やCFDを積極的に取引したい人 | 公式サイトへ |
広告:A8.net提携案件。NISA対応状況は各社の公式情報に基づきます。最新の取扱や条件は必ず各社サイトでご確認ください。